スポーツの種類によって筋肉の柔らかさ、固さが異なるとか・・・
筋肉繊維でよく言われる持久力のある遅筋繊維や瞬発力のある速筋繊維!
いろいろな議論があると思いますが、ほとんどの方が望まれるのは筋肉繊維のことはともかくとして柔らかい筋肉を維持したい。そして固い筋肉を柔らかくしたいというのが本音のところだと思います。
そして固くなった筋肉を柔らかくするにはどうすればいいのかについて解説していきます。
水泳の持つ優れた特徴で柔らかい筋肉を維持して基礎的な身体能力と運動能力を手に入れていただきたいと思います。

目次
1. 水泳で筋肉が柔らかい状態を常に維持できるのか?
水泳は子供にふさわしいスポーツであるとよく言いますが、それは筋肉が固まらず柔らかい!
いろんなスポーツへの応用がきく意味から水泳は子供たちが初めて習う運動としてふさわしいのだと思います。
そして子供たちがスポーツ少年団や中学生になっての部活への参加によって、水泳との両立という選択肢は非常に低くなり、水泳からの離脱という現象が一般的です。
特別に水泳への興味、水泳の記録が備わる一部の子供たちがそのまま水泳で選手コースへと進んでいくこともありますが、水泳との両立をする子供たちは非常に少ないです。
1-1. 身体が柔らかい子供たちの水泳
私は定年退職後しばらくジュニアのインストラクターとして子供たちの水泳に携わった経験があります。
そこで子供たちや親御さんにいつも言ってきたのは、




その理由にあげたのは子供の筋肉はいつも柔らかい状態で維持することが必要です。
陸上のスポーツは瞬発力が重要であることからそのスポーツに適合した身体能力が鍛えられますが、
水泳はスピードを争う競技とはいえ、全身運動であり、身体の柔軟性は長く維持することができます。
部活などで他のスポーツをやりながら水泳も続けていくという水泳との両立がもっとも好ましいと思うのですが現実的にはごく稀なケースです。
1-2. 魚の筋肉
水泳はこの記事で言う、柔らかい筋肉を維持することができるという意味を考える場合に
魚をイメージしてもらうとよくわかると思います。
カツオ、マグロ、カジキなどの泳ぎ続ける魚は赤身魚と言われるように赤い筋肉繊維がほとんどでこれは遅筋で持久力を得意とする筋肉です。
一方、ヒラメ、カレイなどの底にじっとしている魚は白身魚と言われ、白い筋肉繊維が優位で速筋で瞬発力が得意な筋肉です。
このヒラメなどは海底でじっとしていて、獲物に出会ったときに一瞬の瞬発力によって獲物をしとめるシーンをイメージしてもらえればよく理解できると思います。
さらにブリ、タイ、アジ、サバなどの遊泳する魚で海流にのって移動するような魚は赤身白身が混在しています。
そしてその全ての魚の筋肉は柔らかい状態を維持しています。
1-3. 筋肉が柔らかいとは?
子供たちが激しい出発力を必要とする運動をすると幼い間にそのような瞬発力だけに頼れば筋肉がこり固まってしまい、柔らかい状態を維持することが難しいというのが私の持論です。
子供たちに瞬発力練習をする場合には十分なストレッチやウオーミングアップやクールダウン、そして必要に応じたマッサージなども必要と考えます。
これは子供たちばかりではなく成人世代にもこの配慮はとても大切だと言えます。
筋肉増強には筋トレがどうしても大切ですが、筋トレの前後のストレッチ、アップやクールダウンは欠かせません。
こうした配慮を常に持つことで、いつまでも柔らかい筋肉を維持するケアになると考えます。
1-4. 筋肉が柔らかい状態を維持するには?


柔らかい筋肉というのはこり固まった状態がない状態をいうのだ私は考えています。
1-4-1. 筋肉が柔らかい水泳の特徴
多くのスポーツ選手がオフの練習バリエーションの一つに水泳を取り入れていますが、これは筋肉をほぐしながら鍛えるという意味とリラックス、気分転換といったマインド効果を狙っての配慮だと思います。
水泳で柔らかい筋肉を作る秘密は水泳が有酸素運動の代表格であるからです。
水泳は同じ運動を繰り返し、その繰り返しも常に浮力、抵抗、水流などの物理的な影響を受けながら筋肉を動かし続けます。
そして何よりも全身運動です。両手両足、体幹部の筋肉とフル活動のフル運転です。
ビギナーから上級者までその筋肉の動きはまるでほぐしながら運動をしているようなものです。
全くのビギナーであったり、上級者のスピード練習以外、筋肉痛や肉離れなどの症状とは無縁だといえます。
それに陸上のスポーツと違ってなぜか必ず、準備運動の意味でストレッチを忘れません。
1-4-2. 水泳経験による筋肉の特徴
まだまだ初心者ままならない頃、やみくもに手足を動かせて泳ぐという光景を思い出しますが、その状態では筋肉はこわばり、陸上で柔らかい状態の筋肉も水中に入るだけで、精神的にも肉体的にも硬直状態が襲ってきます。
でもほんの少しでも泳ぐことができ、25mくらいは泳げるようになると筋肉の動きは一変します。
柔らかくしなやかな動きはとなるのは明らかです。
一説によれば、遅筋は固く、速筋は柔らかいという説で、マラソンランナーの筋肉は固く、スプリンターの筋肉は柔らかいなどというような議論もあります。
でもこれは筋肉繊維の特徴というレベルの話であって、マラソンランナーであれスプリンターであれ筋肉は常に柔らかい状態を維持しておくことが重要でしょう。
ところが水泳というスポーツは競技で考えればクロールを考えてみましょう。
100m、200m、400m、800m、1500mなどと協議種目は泳ぐ距離によって筋肉の使い方は陸上とはまるで違っています。
まず、陸上競技で考えれば100mとマラソンとではどうでしょうか、どちらも同じ走るという運動ですが、
私の感覚では100mは下半身の筋肉はもちろん重要ですが、腕、肩の筋肉も総動員してスプリントを生み出すのではないでしょうか
でもマラソンにおいても下半身の筋肉はもちろんですが、腕や肩はスプリントを生み出すというよりもリズムとかタイミングというようなイメージに感じます。
ところが水泳は100mであれ1500mであれパワーと回転数の問題だと考えています。
水泳の場合どの泳ぎであれ、速さの追求はアクセルの推進力の向上とブレーキに抵抗を最小限にして泳ぐこのテーマは変わりません。
推進力を高めればより強い抵抗を生みますのでその抵抗を上回る推進力が必要となり爆発的な筋肉が必要となります。
100m走とマラソンではまるで異なったスポーツのように私には感じますが、
水泳の場合、100mと1500mそして遠泳いずれも同じ水泳なのだと思っています。
ところが、より速く泳ぐために回転数をあげて推進力を高めようとすると、使う筋肉の疲労度がたかまり固いコルという状態になるのも事実でしょう。
でもスポーツの相対的な考え方として、水泳運動は全身の筋肉が常に柔らかい状態を維持することが可能なスポーツだと言えると思います。
そして陸上のスポーツで偏った筋肉疲労、コリなどの症状をもみほぐすなどのマッサージ効果とリラックス効果をねらった水泳はとても有益だと言えるでしょう。
さらに単なる筋肉のリラックスだけにとどまることなく水泳は呼吸が不自由ですから、呼吸筋が鍛えられ心肺能力の強化も同時にでき、水泳に対する期待が高まっているのだと思います。
2. 具体的なやり方とコツ


私の学生時代、専属トレーナーなどいなかった時代です。
選手同士で先輩・後輩分け隔てなくお互いに身体のケアをした経験があります。
私は主将だったこともあり、人一倍自分の身体のケアはもちろん、各選手のケアも徹底的にやりました。
各選手、個人ごとに状況は違っており、選手ごとに固くてコッているとろこをいち早く見つけ、揉みほぐす時間をできるだけ作っていました。
2-1. いち早くコリを見つけ柔らかくする
私たち選手経験があるものにとっては身体を触ってすぐにコリを見つけることができますが、被検者の痛みやこわばりなどの自覚症状を手掛かりにいち早く見つけることができます。
両手を開き、剣にしてトントンとまな板の上で叩くように幹部に刺激を与えるとかなり筋肉が柔らかくなってきます。
競泳の場合の特徴としては肩、腕、腰、太ももなどが特徴的に固くなります。
固い部分をリズミカルにトントンと叩いてやると柔らかくなり被検者はとても気持ちよくなります。
揉むのはかえって筋肉のこわばりが悪化する場合があると聞いていたので主に叩く動作を主体にしておりました。
今思えば揉むことがなぜよくないのかはいまだに理解できませんが、刺激という意味ではどちらも良いとは思いますが、トントンと叩く刺激は本当に筋肉が柔らかくなるというのは身をもって経験していますからおすすめです。
自分で手が届くところの筋肉を柔らかい状態にするには両手の剣でトントンと叩くマッサージは有効です。
2-2. ストレッチを忘れずに
それから筋肉を柔らかい状態に戻す最善の対処法は何と言ってもストレッチでしょう。
一人では限界がある場合も二人で組んですれば全身ストレッチが可能ですので二人で組んでするもの効果的です
水泳をやることで、こわばった筋肉を柔らかい状態にする代表的なストレッチを紹介します。
2-2-1. 肩
肩のこわばりは壁を前にして立ち、壁の一番上を触るイメージで肩関節や肩の筋肉を伸ばし柔らかい肩にしてやります。
肩関節や筋肉が固くなっている場合にはこの壁ストレッチはとても効果的です。
2-2-2. 下半身
下半身のこわばりはプールのスタート台や机やテーブルに手をついてアキレス腱を伸ばすイメージで太ももなどの固くなっている筋肉を伸ばしましょう。
片足ずつ入念に伸ばしてやれば、筋肉が柔らかい状態になっていきます。
ジャグジーに入ってこれをやるのも効果的です。
2-2-3. 腰、股関節
俗に股割りとも呼ばれているものですが、両足を可能な限り広げ可動域を少しずつ広げていくオーソドックスなストレッチです。
二人で両足の裏を合わせ、二人で両手を握り合い交互に股割をするのも楽しいです。
2-2-4. 水中ウオークや水泳
スピード練習の後、出来るだけゆっくりと歩いたり泳ぐことで筋肉をほぐし、柔らかい状態に戻す、クールダウンに時間を割くのも大切ですので
スピード練習後に柔らかい筋肉に戻すことはスイマーにはとても重要なことです。
3. 常に筋肉は柔らかい状態に!


そして加齢が加わると背骨の歪みなど身体的な弊害へと悪化する場合もありますので、常に柔らかい筋肉にしておく必要があります。




柔らかい筋肉を維持するのはもちろんのこと、ちょっとしたストレスによるコリなどもすぐに見つけてもらえます。
それに消化器官が弱っているとか、最近アルコールが多いですねとかピシャリと当てられることもあって、私には専属トレーナーの位置づけです。
そして水泳はコリがないことも私には柔らかい筋肉保持に大切なことです。
デスクワークが多いと足腰の血行が悪くなり部分的にコリが起こります。そんなとき気分転換もふくめて水泳はとても効果的です。
そのためにも水泳はとても効果的でリラックスできるスポーツです。いやスポーツの域を超えていると思います。
どうぞ、可能なら水泳を生活習慣の中に取り入れていただくことをお勧めします。
4. まとめ
水泳が固くなった筋肉を柔らかい状態に戻すのには、とても効果的な運動であることにスポットをあてて述べてきました。
その中で、私自身の経験として競泳のためのスピード練習などでこわばった筋肉を柔らかくする場合も例にあげても解説してきました。
いかがでしたでしょうか、楽しんでいただけたでしょうか!
有酸素運動の代表格でダイエットなど健康維持にとても有効な水泳が理想的な柔らかい筋肉を維持するにもとても効果的なこと
そして、水泳を単なるスポーツとしてとられるのではなく、健康維持のためのツールとして位置付けていただけたらとても喜ばしいと思います。
それも単に泳ぐだけでなく、ストレッチやマッサージなども取り入れて常に心も身体も柔らかい状態を維持していきたいと痛感しています。
最後まで読んでいただき心から感謝しています。
それから次の記事もとても興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。



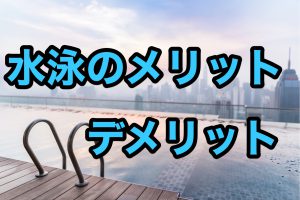

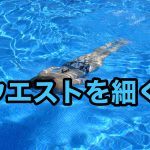






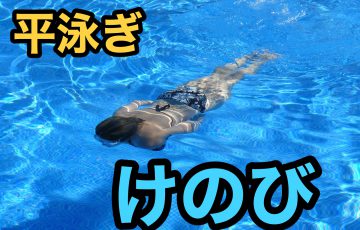

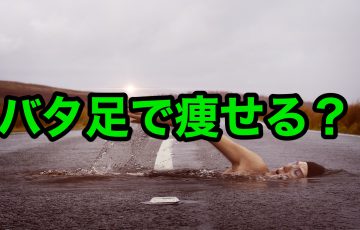











けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。