水泳で言うところのストロークとは「連続する泳ぎの中で1単位あたりの腕で水をかく動作」を言います。
そして「ストロークが上手になるコツ」といった表現をします。
ストロークを端的に言えば
たとえばクロールですと1ストロークは右・左1回ずつで1動作が完結します。
そして1ストローク内で打つバタ足が2回であれば2ビートキック、4回であれば4ビートキック、6回であれば6ビートキックとなります。
また平泳ぎやバタフライでは左右対称ですから、1ストロークは1回の腕のかき動作で完結ということになります。
背泳ぎはクロールと同じストロークになります。
水泳におけるストロークのコツを自分のものにして華麗なフォームをマスターしましょう。

目次
1. 水泳のストローク種目毎の上達のコツ
それぞれ水泳における4つの泳法ごとに見ていきましょう。
それぞれに特色のあるストロークですが、共通するコツ、そして個別泳法に特徴的なコツについて理解が深まると思います。
1-1. クロール
では水泳で最初にマスターするクロールです。
エントリーの瞬間は指先からゆっくりと手を入水させます。
ひじを高く保ったまま入水、水を下に押すイメージでストロークが始まります。
前の腕全体でより多くの水をキャッチするイメージのストロークとなります。
手で水をかいて身体の下に引き寄せるようなプル動作がストロークの基本です。
ストローク中はひじを曲げ、手を抜くときはひじから抜くイメージです。
より速く効率的に泳げるようにストロークをしっかりと練習しましょう。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
1-2. 背泳ぎ
水泳種目、次は背泳ぎです。
ストロークのイメージですが、親指から抜くように水の中からリカバリーし、一番身体から遠いところに小指サイドから入水するようなイメージでストロークすると身体の体制が保ちやすいです。
身体がローリングをしているので決して身体の背中側をかいている訳ではありません。
このイメージの違いが背泳ぎ最大のコツとなります。
リカバリーは親指から抜き親指をしっかりと見つめましょう。こうすることで姿勢の安定につながります。
詳しくは以下の記事が参考にしてください。
1-3. 平泳ぎ
次に平泳ぎに移ります。
ひじを高い位置に維持したまま外側へ水をかきます。
手のひらで水を後ろへ押し出すイメージのストロークとなります。このとき脇をしっかりと締めるまで手首をしっかりと回しましょう。
両手が胸の前に来て合掌するようなイメージです。
ひじをまっすぐ伸ばし、両腕を一番遠い前方へ肩甲骨をしっかり伸ばしてリカバリーです。
より効率的に抵抗の少ないストロークを練習しましょう。
詳しくは以下の記事が参考にしてください。
1-4. バタフライ
水泳最後の種目はバタフライです。
両腕で水を下に押すようにプルのストローク動作が始まります。
ひじを高く維持して加速をつけて水をしっかりとかきます。
手の指は下を向き、両手は肩幅よりも狭い軌道がしっかりと水を捉えるストロークとなります。
一番加速されている時にリカバリーを迎えますが、しっかりと胸を張って両肩の肩甲骨がくっ付くような位置でリカバリーが始まります。
より速く効率的に泳げるようにストロークを練習しましょう。
詳しくは以下の記事が参考にしてください。
2. ストローク練習のポイント

前章で水泳4種類の泳法についてそのストロークのコツをポイントを絞って解説してきました。
4つの泳法は全く違ったタイプの泳ぎではありますが、基本的に推進力を得る水泳のメカニズムは同じです。
ストロークで得た推進力を最大限活かすために、体幹部の筋肉を使って水中姿勢を真っ直ぐに保ち、水の抵抗を最大限に少なくするというのが基本です。
では水泳におけるストロークの基本的なコツを詳しく見ていきましょう。
2-1. ゆっくりとしたストローク
水泳のストロークの練習はどの種目でも誰もが一番苦労するというか、難しく感じる動作ですが、この一番の理由に上げられるのが呼吸です。
水泳は呼吸が自由に出来ない水中で呼吸は恐怖すら感じる大切な動作なのですが、4つの泳法それぞれが異なる呼吸環境を克服しなければなりません。
ストロークで大切なことはゆっくりとした動作で自分に相応しいストロークを会得する必要があります。
水泳経験の少ないビギナーさんはどうしてもストロークが早すぎて25mを泳ぎ切るだけで体力の全てを消耗させてしまうほどです。
2-1-1. 呼吸
水泳4泳法の中で、背泳ぎだけは仰向けですが、ストローク中は自由に呼吸ができる状況ではありません。
ストロークと呼吸のタイミングをしっかり練習しましょう。
従ってストロークをコントロールできるコツの一つに呼吸がありますので呼吸のタイミングをしっかりとマスターしましょう。
しっかりと息を吐いてしまえば顔を上げた瞬間に息を吸うという意識がなくても息が軌道を通って吸息できるます。
そして長い吐く呼吸の時間にゆっくりとしたストロークが実現でき、安定することとなります。
2-1-2. 小指側サイドに集中
水泳においてはどの泳ぎ方もリカバリーを終えて腕が入水エントリーする時に手の小指からひじにかけての裏筋に集中することで最も遠い場所への入水が可能となり、的確に水をキャッチできるコツです。
そしてその手の平からひじまでの全体で水をキャッチするのもひじ曲げ、ひじ高がコツです。
ストローク後半水をプッシュする時は平泳ぎ以外はしっかりとひじを伸ばします。そしてひじからリカバリーとなります。
一方平泳ぎはひじを中心に胸の前で脇を締めるというストロークのフィニッシュを迎えます。
そしてリカバリーを迎えます。リカバリーはしっかりとひじを伸ばすと同時に肩甲骨を可動域いっぱい伸ばします。
2-2. 抵抗の少ないストリームライン
次に水中姿勢(ストリームライン)が水泳においては全ての泳法で、とても重要で自分に相応しい最も推進力を邪魔しないストリームラインを会得しましょう。
この理想的なストリームラインを実現させるためには体幹部の強い筋力が必要です。
この筋肉が十分でないと、下半身が沈んだり、腰が沈んだ湾曲姿勢などと大きな抵抗を受け失速原因となります。
腹筋・背筋に意識して体幹部の水泳をいじするのはもちろん、お腹を凹ませるというコツをお伝えしたいと思います。
水泳においてインナーマッスルを武器にすることが大きな武器となります。/box]
2-2-1. スタート、ターンでのストリームライン
まずスタート、ターン中のストリームラインです。飛び込みスタートの初速は落下エネルギーや壁を蹴るエネルギーなど最小限の筋力パワーで得られる初速です。
この初速を生かして浮き上がり、自分のストロークで初速スピードを維持させる技が大切となります。
従ってスタート・ターンでのストリームラインはいついかなる時でも練習で姿勢チェック、修正、強化を測るとことを忘れないようにしましょう。
浮き上がりスピードでそのレースを支配するといっても過言でなく、私が進言する重要なコツの一つです。
2-2-2. ストローク中のストリームライン
それから平泳ぎ、バタフライのストロークにおいても、スタート・ターンで見られるストリームラインと同じ体勢の瞬間があります。
この時にはスタート・ターンと同様に水抵抗を一切受けないとの強い意思により、ストロークやキックで得られた推進力を生かしましょう。
2-3. キックとのバランスとタイミングのコツ
水泳においてはストロークを活かすために、どうしてもキックから生まれる浮力と推進力の力が必要になってきます。
特に平泳ぎの場合は推進力のほとんどをキックに依存する泳法です。アスリートではストリーク:4、キック:6とよく言われますが、私のイメージではこの4:6のバランスではかえって失速原因となります。
私の場合ですとレースでは2:8ぐらいのイメージでちょうど良い感じです。
したがって、ビギナーさんの場合などはストロークは呼吸のためと意識を変えて欲しいくらいに私は考えています。
その他の泳法においてもストロークはキックとのバランスとタイミングが最大のポイントであり、このイメージが自分自身特有のものになるように反復練習で会得していきましょう。
3. より上手に速くなるためのコツ

前章でストロークを4種目で活用できる効果的な練習方法のコツを示してきました。
ではこれから水泳が上手になるためのコツについてお伝えしていきたいと思います。
3-1. 上手に泳ぐためのコツ
効果的な水泳練習のコツがすなわち上手に泳ぐためのコツなのですが、ここでは練習効果をより一層高めて上手に疲労がなく、傍から見ていてとても上手に見える泳ぎ方です。
そのためには大きなゆっくりと安定したストロークが大切です。そのためのコツに練習ドリルを紹介したいと思います。
そしてこの練習ドリルの趣旨を十分に理解すればとても上手で見栄えのするストロークが実現します。
3-1-1. 練習にパドルを使用する
まず水泳用パドルを使います。水泳4泳法共通です。
一般的にパドルはストローク強化のために使用してプル強化を行いますが、ここで紹介するのは滑らかなストロークを実現するために使用します。
したがって手の平と同じぐらいの大きさのパドルで十分です。負荷を上げないために穴のあるMサイズのパドルが最適です。
パドルをつかって前章で解説したコツを理解してストロークに入ります。
ズレたり、手首に違和感があったりなどの現象が起これば、ストロークに問題があり、その問題はパドルの不安定に即つながります。
スムーズな肩にも大きな負担がかからないような、ご自身が気持ちよくストロークを刻めるようなフォームとリズムを探ってください。
3-1-2. プルブイの使用
次に水泳用プルブイの活用です。手にはパドルをつけても良いですがなくてもかまいません。
最終的には次にあるようなパドル、プルブイ両方を使ったコンビネーションスイムに発展していきます。
平泳ぎの場合もプルブイをはさんでキックは無理かもしれません。でもこのプルブイをはさんでのキックにより、より高速で高度なキックテクニックの練習につながりますのでトライしてみてください。
プルブイの浮力が素晴らしい安定感を体感しながらストロークができることを体感なさってみてください。
3-1-3. パドル、プルブイを使ったコンビネーションスイム
そして最終的にパドル、プルブイの両方を活用したコンビネーションスイムに入ります。
パドルなどがない場合の泳ぎよりもさらにおおきなストロークが刻むことが体感できると思います。
そして一回のストロークで得られる推進力とその推進距離に満足されることと思います。
このパドル、プルブイの用具を単独使用する練習から発展して両方を活用してコンビネーションすることで狂いのないストロークが実現することとなります。
その場合、プルブイの浮力がなによりもありがたいと感じることでしょう。
3-2. より速く泳ぐためのコツ
では次により速く泳ぐためのコツに移ります。
ここまで水泳練習をおこなってきますと、当然ながら、大きなストロークでより速く泳げるようになってきたと思いますが、より速く、自己ベストさらには競技会の1位レベルまで高めたいと思います。
そのために必要なコツについて紹介していきます。
3-2-1. ストローク数を数える
まずは25mのストローク数数え、記録するというものです。
上手になるにしたがってストローク数が減少するという不思議な現象が起こります。
たとえば25mのクロールを例にとれば、ビギナーさんであればひどい人なら30回のストロークを刻んでいる人もいます。
そばでみているともう風車のように両腕が回っています。
あれでは疲れるわ!という感じです。
でも私もそうですが、水泳上級者になれば10ストロークくらいで十分25mに達します。
そのリズムは崩さずにスピードアップするともうすごいの一言です。優雅であると同時になんと素晴らしいスピードなのかと驚くばかりです。
すると、今日の調子とか、いろんなチェックが機能して修正も容易です。
たとえば同じストローク数でパワー5割、7割で泳いでみる。
同じストロークでパワーの違いは所要タイムに影響し、実質1ストロークに要するタイムが圧縮されます。
このパワーの違いを体感してみてください。
次にストローク数を上げて、回転数を上げるのです。そしてパワーは5割です。
そのときの所要タイムを計測します。
こうしたいろいろな組み合わせスピードコントロールプランが出来上がります。
そして来るべき競技会において、自分自身の今の体調や精神状態を加味してレースプランを立てていくのです。
どんなレースプランであっても100mのゴール前25mは回転数はマキシマムなストロークでパワー10割でゴールに突っ込みます。
ゴール前のダッシュは身を見張るものがあると思います。
3-2-2. ターンテクニックを練習する
それからより水泳競技においては速く泳ぐためにそしてストロークを少しでも省エネハイブリッドで泳ぐためにスタート、ターンテクニックの上達は欠かせません。
蹴伸び、ストリームライン、水中姿勢から浮き上がりまでの許されているドルフィンキックなど、ルールに従った技はタイム向上になくてはならないものです。
スピードアップはストロークよりも水中姿勢のほうがより速くが実現されます。
そのためにもストロークよりもターン練習優先されるかもしれませんが、より速くを実現するためにもターン練習やスタート練習も忘れず取り組みましょう。
4. まとめ
以上、水泳におけるストロークの重要性、そしてストロークが上手になり、より速くを実現させるための練習のコツ、そしてイメージの世界でのコツ、あるいはコンディションをチェックするコツなど盛りだくさんでお伝えしてきました。
この記事は私の長年の水泳経験から築き上げてきたメソッドであって、疑義もあろうかと思いますが、参考にしていただければ大きな成果を期待できることと確信しています。
私のようなシニア世代になれば水泳の記録よりも見栄え、優雅さ、そして安定したスピードの保持、これは幾つになって維持していきたいと思っています。
これから水泳を始めた方にもゆっくりと焦らずに泳ぐことが水泳上達のコツだと思います。
是非この記事を参考になさって水泳を楽しく、疲労の残らないストロークの実現に向けて互いにがんばって下さい。
最後に水泳は決してがむしゃらはスピードアップにはつながりません。ゆっくりと優雅に泳ぐことでスピードアップにつながることを申し上げてこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いを頂き心から感謝しています。ありがとうございました。
なお、以下の記事も興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。



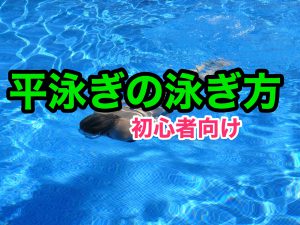





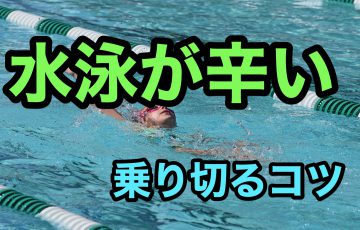

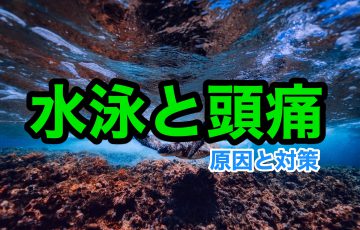















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。