水泳の競技会も時代と共に変遷があり、現在の競技会では屋内プールが一般的となり、計時システムも完全自動化・電子化され、号砲も電子音となりました。
スタートに関するルールとシステム概要、そして過去からのスタートの変遷なども併せて紹介してこれから競技会を目指す人たちやマスターズスイマーを目指す方々のお役に立てれば幸いです。
現在のスタートに関する仕組みとシステムをぜひ理解されて、日常のスタート練習に活かしていただければ幸いです。

目次
1. 【水泳競技のスタート音】計時システム
水泳競技が始まるスタート音発生から選手が飛び込みレースが開始されますが、ゴールの瞬間までの計時システムの概要を今一度詳しくまとめておきたいと思います。
・自動審判計時装置(タイムの計測)
・競技処理コンピューターシステム(記録の処理)
・電光掲示システム(記録公表)
そしてこれらの計時システムが一連の流れの中で正確性と公平性の確保を厳正に運営されています。
1-1. 自動審判計時システム
これらのシステムはスタート台とプール両サイドに壁に設置されてあるタッチ板により正確にラップタイム・ゴールタイム、そして着順判定まで正確に処理されます。
号砲スタート音に対する選手の反応がありスタート台から選手の足が離れる反応時間(リアクションタイム)を瞬時に計測して同時にフライングの自動判定を行うシステムになっています。
このリアクションタイムが電光掲示板に公表される競技も珍しくはありません。
さらに自由形中距離以上の競技には水中周回計が設置されており、水中に設置された表示器により選手が折り返しの数をチェックできるようにも配慮がなされています。
1-2. 記録処理システム
計時システムで計測されてデータは全てオンラインシステムにより処理され、競技終了後に速やかに電光掲示板に表示されるまでの一切のデータがサーバに保管されています。
1-3. 電光掲示板表示システム
以上のシステムと並行して処理された途中中間結果や競技結果を観客にタイムリーに公表できるシステムがフル稼働しています。
そしてこれら短時間で行われるタイムレースである特徴からシステムの正確性はますます重要度が高まっています。
2. スタートルールを熟知する


2-1. 水泳競技のスタートルール
まず最初に競技会でのルールはどうなっているでしょう。見ておきましょう。
2-1-1. 競技会ルールにおけるスタート規定
水泳競技におけるスタートについては日本水泳連盟競泳競技規則には以下のように定められています。
第4条 出発
1 自由形・平泳ぎ・バタフライ・個人メドレーのスタートは飛び込みによって行う。
⑴ 審判長の長いホイッスルにより競技者はスタート台に上がる。
⑵ 出発合図員の号令(take your marks)によって、競技者はスタート台前方に少なくとも一方の足の指を掛け、速やかにスタート姿勢をとる。その際、両手の位置に関する規定はない。
⑶ 全ての競技者が静止したら、出発合図員はスタートの合図をする。
2 背泳ぎ・メドレーリレーのスタートは水中から行う。
⑴ 審判長の1回目の長いホイッスルによって競技者は速やかにプールに入る。
⑵ 2回目の長いホイッスルによって故意に遅らせることなくスタート位置につく。
⑶ 出発合図員の号令の後、全ての競技者が静止したら、出発合図員はスタートの合図をする。
現在適用されているルールでは事細かに手順が明記されています。このルールに則って水泳競技のスタートが淡々と進められ運営されているのです。
号令も(ヨーイ)ではなく(take your marks)と国際大会と同様に英語で発せられるのです。ドキドキしますよね。
さてスタート音についてその変遷を見ていきましょう。
2-1-2. スタート手順
先ほどの競技規則では
⑶ 全ての競技者が静止したら、出発合図員はスタートの合図をする。
とあります。すなわち全ての選手が静止したら直ぐに号砲が鳴るのでしょう。
そして次に
4条 出発
1、2は省略
3 出発合図員の前にスタートした競技者は失格となる。失格が宣告される前にスタートの合図が発せられていた場合、競技は続行し、フォルススタートした競技者は競技終了後失格となる。>出発合図の前に明らかにフォルススタートしたと見なされる場合は、出発の合図はせず、その競技者は失格とする。他の競技者については、元の位置に戻り再出発をする。その場合、審判長は長いホイッスル(背泳ぎの場合は2回目の長いホイッスル)から出発の手順を繰り返す。
引用:日本水泳連盟競泳競技規則
以前のルールではフライングがあればスタート音であるピストル音を2回鳴らしてフライングスタートであることを宣言したものです。
スタート音が2回なれば選手は立ち止まり、元に戻ってスタートのやり直しをやったものでした。
でもスタート音の前にフライングした者は失格を宣言され、スタートのやり直しとなります。
2-2. 目視確認から全自動計時
さらに前述の目視確認による計時から近年の全自動計時システムへと変遷が行われてきました。
全自動計時システムとは、スタート合図は計時システムと連動されており、号砲とともに一斉計時スタート、そしてゴールはタッチ板の採用により、選手がゴールしたタッチにより自動計時がなされというシステムとなりました。
もちろんこの全自動システムのトラブル回避のため、計時員によるバックアップ計時も併せて行われ万全が期されているのです。
この変遷の推移がスタート音にも現れており、ピストルの破裂音から、電子音へと変わってきたのです。
そして私もいつも関心があったのはスタート音がどこから聞こえるのかが不思議でした。
今までのピストル音は遠いところから鳴っているように聞こえていたのですが、マスターズ水泳大会の電子音はなぜかすぐ近くで鳴っているような不思議な感覚があったのですが、聞いてみればスタート音はスタート台にどうもスピーカーがついているようなのです。
背泳ぎではかなりのボリュームかもしれません。




3. スタート音に全集中で自己ベスト


前章までにお話ししたように、高い性能を持った水泳競技計時システムは国内外のトップ競技会に止まることなく、私たちが楽しみにしているマスターズ水泳大会においても準拠され、国際大会とほとんど変わらない制度のシステムに支えられています。
従って我々、選手側もより高い制度のスタート技術でもって対応しなければなりません。
スタート音にいかに早く反応するかが問われることになります。
日常の生活の中からスタート音に反射的に反応するトレーニングが必要となります。
水泳競技のスタートはあくまで反射力、スタート音で反射的に飛び込むという反応です。
耳でスタート音を聞いて筋肉が飛び込む準備に入るというものではなく、スタート音を認識後瞬間的に飛び込んでいなければなりません。
従って、スタートのtake your marksのアナウンスではもうスタートに必要な全ての筋肉も準備完了、縮みきった筋肉と神経の解放を待つだけというのがスタート音を聞く瞬間の静止状態だと思います。
スタート音を認識すれば飛び込むというよりは、スタート音で泳ぎだすというイメージですね。
3-1. 反射力トレーニング
こうした反射力をトレーニングする練習には次のような状況が適していると思います。
・時報やアラーム音によるスタートイメージ
・陸上クラウチングスタート練習
スタート練習には何と言っても陸上競技のクラウチングスタートの練習が最適です。
陸上でのクラウチングスタートを十分に練習しておけば水泳競技のスタートにもとても有効です。
これは自宅でもどこでも練習ができると思います。
何も走り出す必要はなく、反応を高める練習なのですから・・・
3-2. スタートフォームを決める
・スタート台を持って体重・重心を引いてエネルギーを溜めるか、それとも体重・重心を極限まで前に出すかです。
いずれも、どちらが良いのかは選手各人が決めなければなりません。
色々試してみてどの方法がもっとのプールハーフラインまでのタイムを測定して決定すべきだと思います。
そしてスタートの感触の方法がベストです。
その時々においてどのスタートフォームがいいのかは経験が浅いときにはバラツキがあると思いますが、少しずつ経験を積み重ねて自分独自のスターティングフォームが決まってくることでしょう。
3-3. フライングが激減


前章でスタートについてのルールと歴史的な変遷について述べてきたのですが、私が感じる中で特出すべきことはフライングの激減です。
その理由を追跡してみましょう。
実は私も学生時代はフライングをよくするタイプでした。
というより、年齢の若い人は経験が浅く、フライングには気をつけるのですが、年長者は故意にフライングをしました。
レースの敵に揺さぶりをかける心理作戦と同時に軽いウオーミングアップを兼ねるといった悪意があり、私も年長になればよくしました。
それは3回までのフライングが許されていました。従って、1レースに一つや二つは必ずフライングが当然のようにあったのです。




それに、私だけが感じるのかも知れませんが、スタート音が極めて早いということです。
全員が静止してからの間合いにスターターの個性があって待てないといった状況からフライングに陥るケースがあったのも事実なのです。
それが最近は選手がtake your marksによって選手の静止するまでの時間も短く、静止を確認したらすぐに号砲を鳴らすので、とてもスタート音が早い気がしてなりません。
4. まとめ
以上水泳競技におけるスタートについてその手順やテクニックなど、そして過去からの変遷や現在のスタートとそのシステムについて詳しく述べてきました。
いかがでしたか?お楽しみいただけましたでしょうか・・・
私も長い水泳歴の中で数えきれないほどの公式レースを経験してきましたが、この歳になってもスタートは言いようのない緊張感があります。
でもこの緊張感があったればこそ、今まで続けれたモチベーションだったと思っています。
一瞬のスタート音でこれまでの練習の成果が試されるという晴れ舞台の号砲なのです。
組織がしっかりしているクラブに所属されているスイマーの皆様にとって日々の練習から飛び込みスタートを含めたダッシュ練習ができると思いますが、私のようなマスターズスイマーにとってスタート音を聞いて練習できるのは競技会当日しかありません。
従って、競技会当日のセレモニー前の公式スタート練習は最高の練習機会です。
さらに、競技会場所を選ぶ際には、ウオーミングアップができるサブプールで飛び込みスタート練習ができる競技会はおすすめです。
最後にスタート音を聞く前にフライング・フォルススタートをしないように気をつけられるよう願って、この記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いいただき感謝しています。ありがとうございました。
なお以下の記事も興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。






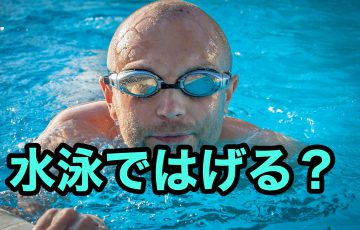


















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。