「子供にスイミングスクールに通わせているんだけど、思うように背が伸びない!」
「うちの子供はスイミングに行くようになってすごく背が伸びた!」
「背が伸びない子供には水泳がふさわしい!」
などといろんな悩みや意見があり、水泳と身長についても様々なサイトがありますが本当のところはどうなんだろう。
どうぞ子供さんには遊び感覚で楽しく水泳に取り組んでほしいですね・・・

目次
1. 背が伸びない原因
まず身長についてWikipediaによれば
個人の身長は主に成長ホルモンとそれを刺激する女性ホルモンの分泌によって左右される。女性ホルモンは成長ホルモンを刺激し身長の伸びを促すと共に骨端線の閉鎖を促し、骨端線が閉鎖され成長ホルモンを止めてしまう。 wikipediaより
との解説があります。
私の場合は小学生の低学年までは背が低かったですが、高学年から飛躍的に伸びて本格的に競泳の練習を始めた高校生の卒業時には178㎝の人生最大身長となりました。今は177㎝の身長です。
年間身長伸び率でもっとも伸びたのは中学生の後半から高校生の半ばあたりではなかったでしょうか。
今では178㎝は標準的男性だと思いますが50年も昔においては目覚ましい身長の伸びで背の高い大柄男性だったです。
ところが両親はともに背が低く父が155㎝、母は145㎝で弟も165㎝と小柄で親戚も小柄な人が多いですから大柄な私だけは少し奇異に映っていました。
この私自身の急激な身長の伸びは水泳をしていたからだと思いますが、それは私の場合であって科学的な確証があるわけではありません。
上記のWikipediaにあるように成長ホルモンの活躍するタイミングと水泳とのバランスとタイミングそして当時の豊かではない暮らしの中でも規則正しい生活が大きな要因だと考えています。
1-1. そもそも背が伸びないとは?
背が伸びないということは成長していないと同意語ではないでしょうか。
先ほどのwikipediaにある骨端線についてですが、子供の腕や足など長い骨の両端にある軟骨が黒く線を描いています。
この部分が伸びることによって背が伸びると言われています。
従って背が伸びないというのは骨端線のところが伸びないと言えると思います。
そして男性と女性を比較すると女性の方が早くこの部分が伸びなくなり、男性よりも背が伸びない、また大人になると、この部分が固い骨になってしまい背は伸びないわけです。
「うちの子は背が伸びないので将来が不安」などと感じていらっしゃる親御さんも多いと思います。
骨や成長ホルモンの問題は目に見えないだけに不安なのですが、ご心配なら一度、医療機関で検診を受けて科学的データなり根拠なりを確認されるのも良いかとは思います。
ともかく、問題は背が伸びるためには、何事もまずは
・「よく食べて」
・「よく遊ぶ」
に尽きると思います。
それでは、この三つの睡眠、食事、遊ぶ(運動)についてそれぞれ見ていきましょう。
1-2. 睡眠
子供の成長において睡眠はとても大切な問題です。
これは乳児期、幼児期だけのことではなく、思春期ごろに背が伸びない状況になるまで言えることで、いや大人になっても命のある限り、睡眠は重要です。
このような意味で睡眠は重要です。
幼い頃の生活週間は一生涯を通してその人の肉体と精神を形作るに欠かせないもの。生きていくための根幹です。
私は両親から午後10時から2時まではどんなことがあっても寝ていなさいと所帯を持ってからも厳しく言われてきました。
そして子供の頃から両親の就寝時間は午後9時でした。
科学的に言えば成長ホルモンの分泌が活性化するのは眠り始めてから3時間くらいの「ノンレム睡眠」の時間帯とされていますから私の両親のしつけは本当に的を得たものであった頃を今更ながら感謝しています。
テレビは食事中には見せてもらえず、結局テレビとは縁遠い人生です。
その甲斐あってか横になったらお休み3秒で睡眠に苦労することはまるでありません。
そして私の身長はこの睡眠効果に得るところは大だったと言わざるを得ません。
でも同じ暮らしをしていた弟は背が高くないので彼にとってはこの睡眠が効果を発揮しなかったわけで、よく寝るというだけで背が伸びるというものでもなさそうです。
とは言え、睡眠による成長ホルモンの分泌如何はとても大切な要素です。
1-3. 食事
背が伸びないというのは身体がどんどん大きくならない状況です。
1-3-1. 食事習慣とバランスのよい栄養素
子供時代に大切な食事習慣というのは3度の食事で栄養のバランスの良い食事だと思います。
朝は食べないとか軽くというのは子供の食事としては好ましくないと私は思います。
また、骨の成長にはカルシュウムが必須の栄養素ですが、カルシュウムだけでは背を伸ばすのは十分ではありません。
マグネシュウムやビタミン群などバランスの良い栄養素が必要というのが通説です。
この点についても私の子供時代の食事を振り返ると昔のことですから、今ほど裕福ではなく、豊富な食材の十分でなかった時代です。
でも朝食事、夕食の自宅で食べる食事は粗食でしたが献立を思い出すと、
朝(7時) :ご飯、味噌汁(わかめ、豆腐の具が定番)、漬物、めざし
夕(17時):ご飯、肉じゃが、ほうれん草、豆腐料理、煮魚
昼(12時):学校での食事、パン食
こんな食事習慣だったことがはっきりと思い出され、習慣としてしっかりと身についています。
今考えれば、質素とは言え、正にバランスの良い日本食だったと思います。
高校生時代には競泳の練習に明け暮れ、エネルギー補給のためにこの3度の食事の他に3回も食べていました。
ここでもう一つ特に大切な栄養素があります。
1-3-2. タンパク質
それは骨を伸ばすためにはタンパク質が欠かせません。
このタンパク質にしても我が家では大豆食品、魚類からしっかりと摂取していたことが言えます。
この食事にしても私の兄弟は同じ食生活であったにせよ、違いが出ていますが、睡眠同様に重要な要素です。
1-4. 遊ぶ
そして三つ目の要素に遊ぶ(運動)があります。
子供には遊びが必要なのではないでしょうか・・・
背が伸びない原因の一つと考えらるのは骨に適度な刺激が必要です。
そして過度な刺激は逆効果となります。
子供時代に過度な負荷や必要以上に激しい運動は禁物と私は考えます。
この運動について私の兄弟は決定的な違いがあります。
私と弟は2歳違いの兄弟ですが、私が本格的に競技選手としてデビューしたのは高校生になってからで、幼い頃から水に入るのが大好きでした。
でも中学生までは部活と言えるものも充実してはおらず、水泳といっても遊びの域をでません。
でも弟は2年違いですが陸上、テニスと激しい練習をしていました。
この運動の違いこそ、背が伸びない弟と背が伸びた私との違いを示す唯一の要素だといえそうです。
もし遺伝的な関与があるなら、親族を俯瞰しても我が家背の低い家系ですから、もし私も激しい運動をしていたら背が伸びない状況であったかもしれません。
ではここで運動に焦点を絞って考えてみましょう。
2. 水泳との因果関係

運動の必要性は先の睡眠と食事と併せて重要なのですが、
子供達が大好きな遊びは走ったり、飛んだり、投げたり、そして泳いだりと本来人が持つ能力の全てが遊びの中に生かされています。
その全ての運動が必要なのではないでしょうか、走っているだけ、泳いでいるだけでは背が伸びない原因になりうるかもしれません。
私の場合、水泳の比重がやはり多いですが、子供の頃というのは温水プールはありません。
どうしても冬季は水泳以外の運動遊びをしていました。
そして弟と同様に走るのも飛ぶのも大好きで高校時代でも陸上部で走っても遜色のない脚力がありました。
そして水泳以外にも飛んだり跳ねたりと屋外で走り回って遊ぶのが必要なのではないでしょうか。
屋内に閉じこもってばかりというのはやはり問題があるのかもしれません。
そしてもう一つ大切なことは常に背筋を伸ばす姿勢に対する躾が重要である点を指摘したいと思います。
2-1. 姿勢を正す
背筋を伸ばして姿勢を正すというのは健康のためにも成長のためにもとても重要なことです。
姿勢がよくなることも背が伸びる条件の一つと言えるでしょう。
また姿勢が良いだけで背が高く見えます。
この姿勢の問題も、子供の頃に鉄棒などにぶら下がる、逆上がりや逆立ちなどで遊んだことはとても重要でやはり外で友達と学校で遊ぶというのは意味がありそうです。
この姿勢の問題から発展して水泳は姿勢を正す意味でもとても効果的な運動なのです。
2-2. 水泳で遊ぼう
でも教える側に立てばクロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライと4つの泳ぎを指導して、さらに上級者になると潜水や横泳ぎやスカーリングなどを教えていきますが、これら泳法指導は子供達は好きではありません。
水泳スクールといってもプールで過ごす1時間程度は徹底的に遊びたいのです。
その子供達の欲求にどう答えていくかが課題ですが、進級ごとにワッペンを与えるなど向上心を煽り、継続させる工夫が必要なのですが、
2年ほど通うとめざましく背丈が伸びて大きく成長する姿は本当に心奪われます。
2-3. 背が伸びないのは
水泳をしているのに背が伸びないというの考えてみると、次のような要因が考えられます。
そして水泳で楽しく遊ぶことができれば背が伸びないと言うのは運動という側面から見れば少々考えにくいと思います。
したがって水泳で背が伸びないというのは水泳が好きになれないというのが原因ではないでしょうか。
2-3-1. 水泳に対する恐怖心
幼児期において水泳を始めて経験する子供達が一様に超えねばならない恐怖心が考えられます。
幼保園時代から水泳を始めた子供さんは小学生になる頃にはほとんどが水泳大好きとなりますが、これは水泳が好きというより、水の中で遊ぶのが好きと言うのが正しいところでしょう。
でも小学生から水泳を始めると言うのはその恐怖心は増幅してきます。
そして背が伸びない状況を確認できる前に退会してしまうケースがほとんです。
2-3-2. インストラクターや施設への不満
水に対する恐怖心とか水泳が嫌いというわけでなく、指導者や施設に対する不満から水泳が楽しくないという場合があります。
この点は施設側のたゆまぬ努力、研鑽が必要でしょう。
私もインストラクターになりたて頃、
「私に触らないで」「いつになったら名前を覚えてくれるの」「なんで遊ばないの」「バタ足は嫌い」・・・
こんな不満を子供達からよく聞きました。
それなりに私も努力して勉強をしました。私の資質の問題で退会者が出たことはなかったのが幸いでした。
2-3-3. 友達ができない
友達ができないというのも水泳を続けるモチベーションの維持に支障があります。
上記に共通するネガティブな感情が子供に存在する場合、骨に与える刺激も健康的だとは言いがたく、ある意味ストレスが成長を妨げると思います。
やはり背が伸びないリスクを払拭するためには、のびのびと水泳が楽しくなければならないと思います。
2-3-4. 過度な運動
水泳が大好きだけど、平泳ぎができない、クイックターンができないという壁にぶち当たった時進級できずに停滞期が訪れます。
このようなケーズで、同じ練習ばかりすることになります。
大好きだった水泳が嫌いになってくる障害であると同時に偏った練習になります。
そのことで、その子供には過度な運動となる場合も出てきます。
またトントンと進級するのですが、より高いレベルに入るためには記録という基準記録の突破が必要となり停滞期が訪れます。
この停滞期に過度な練習となるケースがあります。
でも水泳の場合、競泳の域に近くなりますが、あくまで激しいインターバル練習などハードな練習をさせないのが一般的です。
背が伸びない原因というのは精神的な楽しくないというのが原因ではないでしょうか。
私も経験していますが、楽しければ泳ぐ度に、自己ベストが更新され大会に好成績、ますます楽しくなります。
このような時こそ、飛躍的に背が伸びました。
背が伸びないというのは一時的な問題かもしれないですが、ともかく楽しくないのだと思います。
3. 運動嫌いの子供たちのためのアドバイス

運動嫌いの子供達が家に閉じこもって外で遊ばないというのは背が伸びない大きな原因の一つであると思います。
とはいえ、子供自身に問題があるとか友達がいないなど色々なケースがあると思います。
そんな場合には是非、水泳スクールの入会を検討して欲しいともいます。
医療機関によるカウンセリングやスクールでも懇切丁寧な指導などが得られると思います。
また、普通の塾と同様に経済的負担も軽く、楽しく通わせることができるのではないでしょうか。
背が伸びる時期に伸びないリスクだけは避けたいところですから遊び感覚で通わせるのはお勧めです。
3-1. 水の中で遊ぶ
水泳スクールに通うことは学ぶというよりは、遊び感覚で子供達は楽しく過ごせると思います。
その道のプロであるインストラクターが面倒を見てくれるはずです。
最近あまり背が伸びないと感じられるのであればこのスクールのような何か積極的な遊びを考える必要があるでしょう。
3-2. 運動にこだわらない
背が伸びないリスクを回避するために、運動が必要と言っても幼いころから、激しい筋トレとかハードで過度のトレーニングは骨の成長にとってはリスクがともなうと私は考えています。
まして子供さんが運動嫌いであるなら、なおさらです。水泳の他にも、本人の嫌いな運動をするよりは、屋外で遊ぶ工夫が必要だと思います。
例えばキャンプやハイキングに行くとか、ジャングルジムやブランコなど公園にある器具を使って遊ぶなど、屋外で遊んで過ごす機会を設けてやるなどの配慮が必要でしょう。
4. まとめ
背が伸びないという悩みの改善について水泳の場合を例にとって詳しく解説してきました。
特に私は子供の頃からずっと水泳に慣れ親しんでいますのでその経験や私の家族の状況との比較事例も参考に紹介させていただきました。
いかがでしたでしょうか、参考になり、またお楽しみいただけたのではないでしょうか・・・
背が伸びる、伸びないという身体の成長についてはやはり、なんといっても繰り返しになります、
良く寝て、良く食べて、良く遊ぶ」だと思います。
この3要素を子供時代に習慣づけられた人は大人になってもその習慣が身についているため、加齢とともにその時々の心身ともに訪れるリスクに対して抵抗力が備わっているのではないでしょうか。
特に運動については難しく考えるのではなく遊び感覚で取り組まれることが子供の成長には一番ふさわしいことだと思っています。
私はこれからも水泳は遊び感覚です。
競技会にでるのも遊び感覚です。
トップアスリートとしてチームや地域や国を背負うような大それたモノでなく、あくまで趣味、遊び感覚が今の私にはちょうどいいと思っています。
以上、最後まで読んでくださり、心から感謝しています。ありがとうございます。
それから、次のような拙記事もとても興味深いと思います。読んでいただければより水泳に対する理解が深まると思います。









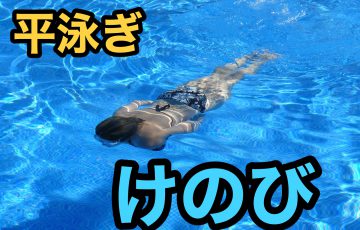















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。