水泳選手は一様に肺活量が凄いという印象を持たれていると思います。
そしてより一層肺活量を高めるためにペットボトルや市販されている器具を使ってトレーニングをしなければならないと考えている人たちも多いと思います。
肺活量について詳しく解説していきたいと思います。
また一方では肺活量を高めるために水泳を始める人もいらっしゃると思います。
実は私自身、高校生の頃肺活量は6000ml超もあり、その記憶は今でもしっかりと覚えています。
それは凄いと言われ有頂天だったからです。
その当時の記憶では6000を超えていたのは私とブラスバンド部員とラグビー部のキャプテンの3人でした。
ブラスバンドやハードな運動をしているアスリートは肺活量が凄いのだと勝手に考えていました。
正しい肺活量の知識をしっかりと学び、偏ったトレーニングをしないように気をつけましょう・・・

目次
1.【水泳と肺活量】トレーニングとの因果関係
画像出典:Wikipedia
水泳は呼吸が自由にできないことからどうしても息を堪える!という動作が必要となり、呼吸筋が鍛えられ肺活量の向上につながると言われています。
海女さんとかダイバーなどは凄い肺活量の持ち主です。
1-1. そもそも肺活量とは
1-1-1. 一般成人の肺活量
健康的な一般成人のは活量は男性で3000〜4500ml、女性で2000〜3000mlと言われています。
合唱団員や歌手そして声優さんなど声を生業にしている人たちの肺活量もきっと驚異的に高いことでしょう。
1-1-2. スポーツ選手の肺活量
スポーツ選手の平均的な肺活量は5000〜6000mlくらいで、運動をしていると呼吸筋が鍛えられ心肺機能が強いので肺活量も向上してきます。
私自身冒頭でも述べましたが高校生の時に6000を超えていて、友達から凄いと言われました。
アスリートで言えば元全日本柔道選手権の連覇を果たした小川直也さんの7000
フリーダイバーで素潜り72mの世界記録を出したこともある木下幸祐里さんで4600
バラエティーで活躍のオードリー・春日さん6800
歌手で俳優の吉川晃司さんで6900
などさすがと言えるだけの肺活量の持ち主が多く、やはりアスリートや声楽家、歌手、俳優などはそれなりのトレーニングの結果が高い肺活量の結果として現れているのだと思います。
1-2. 水泳選手のトレーニングと肺活量
水泳選手と肺活量については私自身が水泳の選手で長く競技練習をやってきましたので自分の肺活量はよく知っています。
先ほども述べたように高校3年生の時には6100でした。以後肺活量を測定する機会がなく、その推移はわかりませんが、50歳の時の健康診断で肺活量の測定項目がありその結果は3000で極めて平均的男性の肺活量までに低下しており愕然としました。
でも50代もバリバリ水泳練習をしてマスターズ水泳で必ず3位まで入賞の賞状をいただいていたので肺活量の低下が特に競技に影響することはなかったです。
1-2-1. マイケルヘルプスの驚異的肺活量
アメリカの競泳界のスタートして君臨したマイケル・ヘルプス選手、2016年のリオ・オリンピックまで数々の記録を打ち立て、オリンピック通算獲得メダル数28個、金メダルでは23個と歴代1位を誇っている。
何よりも通算メダル数のうちほとんどが金メダルというのですから怪物としか言いようがありません。
そして世界選手権では通算メダル獲得数は実に33個、うち金メダルは26個というのですからもやは神的存在です。
その彼の肺活量は15000mlと言われています。
彼の練習量というのがまた凄いです。12歳から水泳を始めて、毎日1日も休まずに6時間の練習をこなしたと言われています。
彼は常に水泳界のトップに君臨して、さらにその地位を維持するために異常なまでの過酷なトレーニングを行なってきました。
豪快でダイナミックなストロークは定評があり、スタート後一番遅く浮き上がりその時点で2位以下を大きく引き離しているのですから潜水能力、抵抗を受けないなどスタートから浮き上がりまでのテクニックにも秀でたものがあったのでしょう。
彼のmメダル獲得種目は個人メドレー、バタフライ、自由形、リレー種目です。
この驚異的肺活量は並々ならない練習と本来兼ね備えた肉体と身体能力の結果作り出されたものなのです。
1-2-2. 瀬戸大也選手の肺活量
次に毎年、着実に実力つけ、2019韓国光州世界水泳のゴールドメダリスト瀬戸大也選手もペルプス同様に個人メドレー・バタフライを得意とする2020東京オリンピックで金メダル候補の一人で和製ヘルプスとの異名を誇っています。
彼の肺活量は6000mlです。これも平均的水準からすれば凄いと思います。でもこの値は私が高校生の時の測定結果と同じ水準なのです。
私には以外に少ないと感じます。
彼もヘルプス同様に天才的スイマーであることは誰もが疑う余地のないところですが、彼の豊富な練習量もまた凄いです。
ペルプスに決して引けの取らない練習量をこなしています。
泳力スタミナと、ラストスパートのパワーは世界NO1のスピードです。
でも6000という肺活量をどう評価するかです。




1-3. 肺活量と運動能力
身体能力が高く好成績を打ち出す選手の共通する要素として肺活量は同レベルの体格の選手と比べて肺活量が高く、逆に肺活量が高いからといって好成績を残せるわけでないということだと考えます。
そして肺活量がたとえ低くても十分な練習で身体を鍛え上げれば十分に結果を残せるのではないでしょうか!
そして結果として肺活量も向上するのだと私は考えます。
2. 水泳選手にとって肺活量とは


では水泳選手と肺活量の関係について述べてみたいと思います。
冒頭でも述べましたがゴールドメダリストの瀬戸大也選手とマイケル・ヘルプス選手等の肺活量についてです。
瀬戸選手の肺活量は6000ml、ペルプス選手は15000、肺活量の容量には倍以上の違いがありますが、彼等の競泳記録を比較してみましょう。
・マイケル・ヘルプス選手の同種目の自己ベストは 4分03秒84(世界記録)
この違いは肺活量の差でしょうか?もちろんこの差は大きな一要因ではあっても、決定的な差は体格の差にあると思います。
小柄な瀬戸選手がマイケルのような2m近い身長を持っていたのであれば、当然ながら10000を超える肺活量を有していたかもしれません。
でも瀬戸選手は世界新記録の更新にまでは至らなくてもゴールドメダリストで世界の第一人者なのです。表彰台での光景はマイケルのような馬鹿でかい選手と肩を組んでいる子供のように小柄な瀬戸選手の姿は日本の誇りです。
従って肺活量を鍛えたからといって水泳で成功するとは言えないと思うのです。
2-1. 持久力もスピードも肺活量とは無縁
水泳は呼吸が制限される中でスピード、タイムを競う競技ですが持久力もスピードも基本的には肺活量は関係がないと私は考えています。
マラソン選手やトラック競技においても同様のことが言えるのではないでしょうか・・・
肺活量は肺臓の大きさ、肺の筋力の差に現れるとは思いますが、瀬戸選手の場合には6000が限界なのだと思います。でもマイケルに自己ベストでは劣るものの全く遜色のない記録を残しています。
ただ彼等が違うのはレースに至るまでのトレーニングに並みの選手とまるで次元の違うものがあると思うのです。
その成果が人並み外れたスタミナとラストスパートでは負けない強さをもち、結果として個人の限界までの肺活量をえる結果となったのでしょう。
2-2. 筆者の経験から言えること
私の場合については当初から申し上げているように学生時代は6000もの肺活量を自慢していましたがシニアになってからはごくごく一般男性の年齢並みの肺活量に落ちています。
でも毎年マスターズ水泳で年齢区分ごとにいつも賞状をもらえる程度の記録を残してきました。
要するに私が目指す水泳とは細く長く幾つになっても水泳を続けていられることが目標であり、学生時代のようなスピードを維持するような練習はシニアになってからはやっていません。
学生時代には25m100本とか50m100本とか信じられないようなインターバルトレーニングでスピードとスタミナをつける練習をしていました。
それはもう無酸素運動に近いような練習だったのかもしれません。そんなトレーニングによって肺活量が大きくなれたのだと思います。
シニアになってからは有酸素系主体のトレーニングしかやっていません。スピードなどは求めず100mを出来るだけ安定したラップを刻めるように長い距離の練習主体でトレーニングをしてきました。
50mのような短い距離は戦わないようにしていました。従ってこうした練習によっては肺活量も大きな容量は必要なかったのだと思います。
2-3. 水泳で肺活量を鍛えるとしたら
もし水泳で肺活量を鍛えるとしたら
・積極的にインターバルトレーニングでノーブレッシングでスピードをあげる練習をする
・スタート、ターンで出来るだけドルフィンキックを使って浮き上がり規則限界15mの許容範囲をフルに活用して浮き上がるトレーニングに務める
・潜水の距離を伸ばすトレーニング
これらのトレーニングによって確実に肺活量の向上が期待できるでしょう。
3. お薦めする効果的な強化方法


肺活量をトレーニングによって鍛えたいと考えている人にとってその方法とは昔からよく言われているペットボトルを使った方法や、パワーブリーズといった肺活量を鍛える器具を使った方法など色々あります。
もし私がオススメするとすればトレーニングをすることで楽しくてそしてその上で継続することで肺活量が向上する方法が良いと思います。
3-1. カラオケ
まずはなんといってもカラオケでしょう。それも一人でカラオケに行って歌いまくる!これが最高に楽しくて肺活量向上には最適だと思います。
もちろん声楽家が行なっているようなボイストレーニングが最適なのでしょうが、基本の発声練習ばかりでは嫌になってしまいますが、一人で歌いまくれば楽しくて、自ずと肺活量は向上していくでしょうね。
特にサビの部分には心を込めてしっかりとお腹から発声をするような気持ちで頑張れば良いのではないでしょうか・・・
歌手や声楽家の肺活量の凄いのには驚かされます。
姿勢を正してお腹の底から歌う感じで歌い込めば良いのではないでしょうか!もちろん、費用がかかりますから一人で車を運転する時とか、一人で誰もいないところを散歩している時とかに歌うのも良いかもしれません。
でも友達とカラオケに行く場合などはマイクを独り占めできないこともあり、あまり効果が期待できるとも思えません。
やはり、肺活量を鍛えるという意識がなければダメでしょうね。
3-2. 吹奏楽器の演奏練習
次に吹奏楽器の演奏です。実は私も学生時代に地域のブラスバンドで活動をしていて練習をやっていたことがあります。
担当楽器はクラリネットでした。肺活量に一番良い楽器はトランペットとかトロンボーンなどの管楽器がベストでしょうね。
楽器演奏の練習にロングトーンというのがありました。一定の音程で長くずっと音を出し続ける練習です。
この練習は肺活量強化には最適だと思います。
ロングトーンは実に難しいです。でも練習を重ねることで少しずつ長く音を出し続けることができ、これこそまさに肺活量の向上効果ではないでしょうか。
私はクラリネットだったので比較的優しかったですが、トランペットなどは音を出すことさえ難しい楽器ですから、その上でのロングトーンですから、管楽器奏者の肺活量は驚くようは容量なのではないでしょうか!
そしてこの理屈で言えばペットボトルや風船などで十分肺活量が鍛えられるということになりますが、やはり楽しくて長く続けられるとすれば楽器演奏といったものが効果的な肺活量トレーニングになりそうです。
私が高校生時代に6000もの肺活量を維持できたのは水泳だけでなく、クラリネット演奏トレーニングも一翼を担っていたのかもしれません。
3-3. 水泳(潜水)
次に水泳です。水泳といっても肺活量をトレーニングするとすれば潜水でしょう。
私が高校生の時には25mプールで1往復は軽いものでした。もちろんこの潜水も水泳トレーニングの基礎があってこそ距離が伸びるわけでズブの素人さんがいきなり潜水をやろうとしてもなかなか思うようには行きませんが、肺活量のトレーニング方法とすれば良い方法です。
少しずつでも距離が伸びるようにトレーニングすれば肺活量トレーニングには楽しく続けられるのではないでしょうか。そして同時に水泳も上手になるというわけです。
3-4. 楽しく続けること
やはり肺活量のトレーニングにしろ、水泳のトレーニングにしろ何だって、長く続けるためには楽しいこと、結果が見える形で確認できることでなければトレーニングは良い効果を期待できないと思います。
ペットボトルや風船やパワーブリーズなどを使ったトレーニングでは面白くなく、気持ちが明るくなりません。
何かやることの副次効果として肺活量が結果として強化されるべきものだと私は考えています。




歌手になるためにまず発声練習の基本をみっちりやるというのは理解できても、肺活量トレーニングをしっかりやるというのはちょっと違うのではないかと思います。
4. まとめ
水泳と肺活量とそのトレーニングの問題について世界屈指のトップスイマーとして君臨した今も世界新記録保持者のアメリカ水泳界の怪物マイケル・ヘルプス選手、日本の和製ヘルプスと名を馳せる瀬戸大也選手を例に両者の肉体的特徴や記録を元に述べてきました。
そして筆者の私の場合も一例としてこの肺活量と記録との関係、そして肺活量の向上に対する水泳の意味について私の考えを示してきました。
いかがでしたでしょうか、肺活量を向上させる意味はどこにあるのでしょうか!
水泳における自己ベストの更新を目指すという大きな目標があって辛いトレーニングに耐えて結果として肺活量が向上したという結果はあっても、
自己ベストの更新をするためには肺活量上げなければならないという根拠は私には見出せません。
あながち、記録更新が実現しても肺活量に大きな違いがない場合もあるかもしれません。
最後に肺活量の違いですが、水泳の場合大きな選手が有利かというと一概に言えません。体格の大きな選手はそれだけ受ける抵抗が大きく、小さな選手は小さくなります。従って体格が小さく肺活量が低い選手が一概にハンディを追うとは言えないと思います。
ただ、大きな選手と小柄な選手とは身長差分だけ泳ぐ距離にハンディがあると私は考えます。
素晴らしい歌手は一様に肺活量は大きくても肺活量が大きくなれば歌が素晴らしいということはありえないことだと私は思います。
肺活量は個人の体格や体質などのよって大きく違い、肺活量の違いは個性なのかもしれません。
水泳のトレーニングでタイム向上の結果がでるためのトレーニングを日々積まれるよう希望しています。
うちの子は水泳が上手にならない!それは肺活量に問題があるから肺活量をあげるトレーニングをしなければいけない!
そんな風に考えるのは私は現実的ではないと結論付けてこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いをいただき心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
なお以下の関連記事もとても興味深い内容となっていますのでご一読いただけたら幸いです。
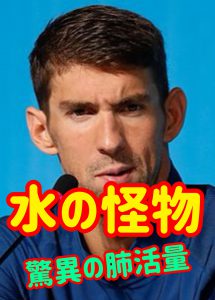
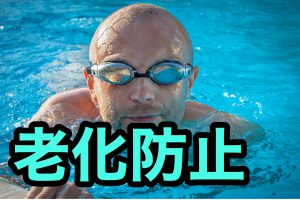



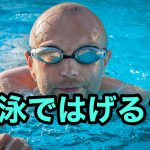



















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。