水泳は有酸素運動の代表格として知られており、最近はダイエット効果を期待して誰もが取り組みたいと考えていらっしゃると思います。
そしてまた、最近脚光を浴びてきている必須アミノ酸のBCAAの摂取が水泳においてもよく議論の的になっています。
水泳は単に有酸素運動だけにとどまることなく、泳ぐことで同時に筋肉トレーニングも加味させて、バランスの取れた身体づくりにも役立ちます。
でもどうしても陸上運動ではないために二の足を踏む場合もあるのですが、水泳後には疲労感や虚脱感も強く回復が遅いこともあり、サプリの服用も有効であるとの考えも多くあります。



目次
1. 水泳の特殊性とBCAAの上手な活用
BCAAとはいったい何?
と初めて目にする言葉である人もいればジムで頑張っている人には常識のサプリ!であったりですが、BCAAとは必須アミノ酸の一種です。
1-1. BCAAの定義(Wikipedia)
分岐鎖アミノ酸(branched-chain amino acids、BCAA)とは、分枝(任意の炭素原子に2以上の別の炭素原子が結合)のある脂肪族側鎖を有するアミノ酸である。
タンパク質を構成するアミノ酸ではロイシン、イソロイシンおよびバリンの3種の分枝鎖アミノ酸がある。
先述の3種の分枝鎖アミノ酸はヒトでは必須アミノ酸であり、筋タンパク質中の必須アミノ酸の35%を占め、哺乳類にとって必要とされるアミノ酸の40%を占める。分枝鎖アミノ酸は臨床では、火傷の治療や、肝性脳症の治療に用いれれている。 Wikipediaより
と定義されています。
すなわちBCAAとは運動時における筋肉のエネルギー源であり、人間が体内で合成できない必須アミノ酸です。
近年、筋肉中に非常に多く含まれているアミノ酸で筋肉の増強・維持にとても重要であるとの認識から注目を集めています。
1-2. 水泳とBCAAとの関係
では水泳とBCAA摂取によりどのような効果が期待されるのか見ていきましょう。
1-2-1. 筋肉の増強・修復
筋肉中のたんぱく質の合成促進、分解抑制、筋線維の損傷修復効果など
1-2-2. 有酸素運動中における効果
有酸素運動である持久力トレーニング中の筋肉中のグリコーゲンの消費抑制と乳酸の抑制など
1-2-3.トレーニング後の影響
例えば合宿など集中した強度の高いトレーニングを一日の中で繰り返し行うなどの状況においてBCAAの摂取・補給はその効果が実証されており、質の高いトレーニングを行うには効果があり、選手のコンディションを維持する効果が高い。
1-2-4. 運動能力の向上効果
BCAAの摂取により運動能力が向上したという研究報告は見つかっていない。
1-2-5. BCAAの摂取方法と摂取タイミング
1-3. BCAAを食物で摂取するには
BCAAは動物性のタンパク質の多く含まれており上記の必要な2000㎎を摂取しようとすると、牛肉では約70g、マグロの赤身で約40g、鶏卵では2個程度、牛乳ではコップ2杯に相当するそうです。
また大豆食品にも多くふくまれており、バランスの良い良質のたんぱく質食品をバランスよく食べる必要があります。
1-3-1. 食品中のBCAA含有量
| 食品名 | BCAA(㎎) | バリン | ロイシン | イソロイシン |
| マグロ赤身生 刺身約8切れ | 4800 | 1400 | 2100 | 1300 |
| かつお | 4300 | 1300 | 1100 | 1900 |
| アジ 中1匹 | 3760 | 1100 | 960 | 1700 |
| サンマ生 中1匹 | 3650 | 1100 | 1600 | 950 |
| 鶏肉(胸肉) | 4300 | 1200 | 1900 | 1200 |
| 鶏肉(もも肉) | 3290 | 910 | 1500 | 880 |
| 牛肉(サーロイン) | 2360 | 650 | 1100 | 610 |
| 卵 1個(50g) | 2610 | 830 | 1100 | 680 |
| 凍り豆腐 1枚(16g) | 1600 | 448 | 720 | 432 |
| 納豆 1パック(50g) | 1305 | 415 | 550 | 340 |
| 木綿豆腐 1/4丁 | 1210 | 330 | 560 | 320 |
| 牛乳 コップ1杯(200ml) | 1360 | 400 | 620 | 340 |
| チーズ 小1個(20g) | 1020 | 320 | 460 | 240 |
引用:独立行政法人 環境再生保全機構データより引用
1-4. 水泳の特殊性
では水泳の運動としての特殊性を見てみましょう。
まず運動強度の違いを他の陸上運動と比較してもとても水泳は運動強度METs値が高いことが言えます。
1-4-1. 運動強度METs値
詳細は次の記事を参考にして欲しいのですが、水の中ということ、また呼吸が自由にできないということで水泳のバタフライはマラソンに匹敵する運動強度の値となっています。
クロールで普通の速さで泳いだ場合には8.3METs値です。これはジョギング7.0に対して高い値となっています。
それに水泳でも背泳ぎや平泳ぎのようにレクレーション的に泳いでいればさほどMETs値は高くないのですが、呼吸が制限される泳ぎ方では格段に値は大きなっています。
それだけ消費されるエネルギーが大きいのが水泳の特色です。
1-4-2. 水の抵抗を受け運動強度がより高い
水泳は水中運動ですからおのずから水の抵抗を受けながら泳がなければなりません。空気抵抗とは比較にならない大きな抵抗を受けます。
このことが人体に与える影響が大きく、より大きなエネルギーを必要とします。
1-4-3. 浮力により下半身のケガが少ない
水泳は地に足のつかない運動です。したがって重力負荷がかかりません。
これは腰や膝に負担がかからずケガなどのリスクがありません。でも筋肉疲労による足がつるなど、乳酸の蓄積はかなり想定されます。
1-4-4. 効果的な有酸素運動
水泳が効果の高い有酸素運動であることはすでにご承知の事実なのですが、併せて、練習のメニュー次第では十分に筋肉強化も同時に期待できる優れた全身運動なのです。
でも先ほども述べたように基本的に有酸素運動であることから、筋肉内に存在するグリコーゲンや糖分はなし崩し的に消費されていきますので筋肉の衰退が起こります。
1-5. BCAAの上手な活用
水泳の持つ特殊性、すなわち膨大な消費エネルギーを考えると、水泳トレーニングの前後、そしてトレーニング中においても適宜、アミノ酸補給によってエネルギー補給は必要であり、BCAAの有効性を考えれば、筋肉疲労は全身疲労に対処するためのBCAAの摂取はとても効果的と考えられます。
ましてアスリートとして競技会を目指しているのであれば、BACCの有効性は非常に高いと思います。
でも水泳を長年やってきた者にとってBCAAで空腹感に耐えられのかという素朴で極めて非科学的な感情を乗り越えられない気がするのです。
さあ、練習の締めくくりにこれから、スタートダッシュ50m×10本とか、さあ今日の大会の最後の決勝レースと言うシーンに立ち至った時に科学的には当然ながらBCAAが威力を発揮するのかもしれません。
30分も経過すればエネルギー補給は万全です。
でも私に言わせれば、BCAAよりもおにぎり2つやバナナ2本を選びます。それは空腹感を満たさなければラストスパートがかけられない!
これが素朴は私が思う感情です。
古き良き時代の私にはやはり、合成された無機物よりも、命ある生きた食材で命を吹き込みたいと思うのは私だけでしょうか・・・
BCAAの製造方法には植物由来の発酵法やコストをさげた合成法があると思います。
天然の仕組みを活かした発酵法で製造されたBCAAを摂取したいところですがいかんせん安価ではないでしょう。



2. 水泳選手とBCAA(サプリ)との付き合い方


さて、水泳に限らず、トップアスリート達とサプリとの付き合い方ですが
2-1. 水泳選手の食生活
アスリート自身にも日々の食生活があり、偏食気味の選手もいれば、寮での合宿生活も種々いろいろあって一概には言えないとは思います。
ある人はサプリで不足する栄養素を摂取している人もいるでしょう。
またサプリは一切摂取せず、自然の食品で食生活一切を賄っているというこだわりの選手もいると思います。
さらに最近ではドーピングの抜き打ち検査がいつあるかわからないという現実もあります。
ネットで簡単に入手できるサプリも決して安易に購入して摂取している選手はいないはずです。
特に水泳の場合には強くて固い筋肉は水泳にとっては比重、浮力、水抵抗と良いことは何もなく筋肉増強目的のサプリなどは不要のものだと考えます。
2-2. 水泳選手とBCAA
またBCAAの摂取によって記録が良くなるという研究結果もまた同様に明らかになっていません。
先ほどドーピングの抜き打ち検査の話をしましたが現在使用が禁止されている薬物がありますが、BCAAの摂取でより速く泳げるようになるというのはドーピングの趣旨からしていかがなものでしょう・・・?
従ってこれらの事からも水泳のアスリートは自然食品による食生活が一般的だと言えるのではないでしょうか。
とはいえ、BCAAの摂取を上手に行って筋肉痛や全身疲労の一助としての摂取するのを決して反対するものではありません。
使用目的、安全性、経済性などを考慮して上手な活用法が望まれるところです。
3. 筆者の栄養補助食品の使用経験例


さて、私自身の長い水泳選手生活において栄養補助食品やサプリとのかかわりについて少しお話ししたいと思います。
水泳の一番ハードなトレーニングをしていたのは何と言っても20歳までの学生時代でトレーニングの質、量ともすごい練習をこなしていました。
3-1. 学生時代の水泳練習と食事事情
毎日泳ぐ距離はトータルで3000~5000mです。競技会前になると1日10000mを泳ぐこともありました。
強化練習の合宿には、さらに泳ぐ距離は格段に多く1日20000mに及ぶ練習をしていました。
当時においては栄養補助食品やサプリと言うのは一般的ではなく、ごく富裕層のアスリートだけが使用したのを珍しく感じていたのを記憶しています。
そんな経験から言っても、さほど競技会のレースに支障を感じたことなく、筋肉の疲労回復も睡眠によって回復するといった日常を過ごしていました。
一方で、食事の量は半端ではなく、1日平均して5食以上は食べていました。いや間食もいれると食事の回数は相当なものだったと思います。
でもいつもやせ型の体形でいくら食べてもお腹が空いている状態でした。
食事の内容は基本的にご飯と味噌汁などの汁物、副食には野菜や魚、肉類などの日本食がメインで2回分の弁当を持参していました。
午前中にお腹が空いて早弁、昼食時には売店でパン類、夕方の練習前にまた弁当を食べていました。
帰宅しての夕食には少しヘビーな肉や魚ベースを副食にご飯中心の食事でした。
我が家は昔から米飯主体で味噌汁と野菜の食生活だったのである意味バランスの良い食生活だったので特段問題はなかったように思います。
でも毎日の炊くご飯の量は相当な量だったと思います。両親と私と弟との4人家族で兄弟二人ともアスリートだったので食費も大変だったことでしょう。
でも私が社会人となり生活が一変しました。
3-2. 栄養補助食品の服用
運動中心の生活から仕事中心の生活に変わりました。その仕事も就職当初から、深夜までの残業で食生活は乱れ、身体はボロボロになりました。
所帯をもってからもこの生活習慣は続き、いきおい栄養補助食品とのお付き合いがはじまりました。
タンパク質由来のものや、ビタミンや鉄分などいろいろなものを試しましたが、あまり効果というものを実感したことは無かったです。
どんな栄養補助食品を摂取してもどうしても学生時代の満腹感というものが忘れられず、満たされない食生活は不規則な食生活による過食と減食の繰り返しでした。
幸い、水泳はずっと続けており、定期的な競技会へのエントリーがあったのでその期間中は規則正しい食生活に戻すなどの配慮を行ったおかげで重篤な病気からは免れました。
でもやはり仕事による不規則な生活やストレスから胃潰瘍や胃ガンなどによって入院を余儀なくされた経験もあり、いかに規則正しい生活と食生活の重要性を思い知っています。
4. まとめ
以上、話題となっているBCAAについて水泳の立場からBCAAの概要と効果について解説をしてきました。
水泳とBCAA、水泳の特殊性からその有効性は基本的にはうなずけるところだと思います。
問題は現状の食生活の状況、摂取する個人の考え方、そして製造方法と価格など、いろいろな面から検討する必要があるように私は考えています。
水泳とともに生きてきた私にとって水泳中そして水泳後の空腹感はいかんともしがたく、それだけに水泳の消費エネルギーが跳び抜けているのかもしれません。
もし仮にダイエット目的で水泳を頑張っているのだとしたら、不用意なBACCの摂取がかえって肝臓などの臓器に負担を大きくする原因になるかもしれません。
水泳をやっている目的、そしてBCAAなど栄養補助食品の使用目的などを今一度十分に理解されたうえで上手で賢明な栄養補助食品との活用を願ってこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いいただき心から感謝しています。ありがとうございました。
なお、水泳関連記事には以下のような興味深い記事もありますのでまたご一読いただければ幸いです。







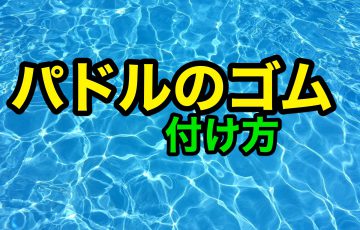

















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。