水泳経験も1、2年と経過すると、マスターズ水泳を目指すシニアも多いことと思います。でもマスターズエントリーとなると大きな問題があります。それは飛び込みスタートの不安です。
そのコツとは繰り返しの練習も大切ですが、練習より大切なことをしっかりと学び、頭に入れておく必要があります。
でも、いつも練習しているプールはスタート台の有する施設であっても常時はほとんど飛び込み禁止!
スタートの練習不足は大きなハンディがあると思います。
このハンディを吹き飛ばす意外な発見がこの記事を読まれるときっとあると思います。
なお、水泳のレースを想定した飛び込みスタートの練習方法について、は次の記事を参考にしていただければ良く理解ができると思います。

目次
1. 水泳の飛び込みスタート
水泳競技を目指すシニアスイマーの読者の方々には競技会を目標に日々トレーニングを積んでおられることと思います。
競技会は所属クラブでの記録会から地域の大会そしてマスターズ大会と各種レースがあります。まずは所属クラブでの記録会があれば是非参加されて緊張感を味わっていただき、その緊張感に慣れて欲しいと思います。
レースは25mのワンウエイレースから200m種目そしてリレーと幾つもの種類のレースがあって観客席から見ているだけで緊張します。その緊張はご自身のレース招集場ではピークに達し、いろいろな不安や心配とネガティブな感情が湧いてくるものです。
もし所属クラブのプールが公式競技が行えるような公認プールであればレースの緊張感を練習の中で体験できると思いますが、一般的なスポーツクラブのプールでの飛び込みスタート台は高さも低く、台上の傾斜もありません。施設によれば飛び込み台さえないプールもあるでしょう。
まずはメンタル面を強くして、勇気を出してレースにエントリーしましょう。
そして私はいかなる競技会であってもレースにエントリーされた貴方の勇気と挑戦する心は賞賛に値し、心から敬意を表したいと思います。競技会エントリーと言う素晴らしいスタートを切られた貴方と共に私もさらに生涯現役を目標に頑張りたいと思っています。
前置きが長くなりました。では早速飛び込みについてその種類と手順をしっかりと理解しておきましょう。
1-1. 飛び込みスタートの種類
では具体的な飛び込みの方法ですが大きく2つの種類があります。クラブスタートとトラックスタート(クラウチングスタート)です。
この2種類は記録を目指すアスリートはほとんどがトラックスタートで飛び込みます。より早い初速度を維持して浮き上がるためにほとんどの選手がこのトラックスタートで飛び込みます。
そして競技会プールのスタート台にはバックパネルがあってこのトラックスタート対応になっています。
では具体的な種類ごとに見ていきましょう。
1-1-1. クラブスタート
クラブスタートはビギナー主体のスタートの方法ですが、両足をそろえてスタートする方法です。この方法は今は時代遅れの感が歪めませんが、私の学生時代にはこのスタートしかなく、身体にこのスタートが染みついていますので、私はこの種類の方法を使っています。
それに私も含めて日々の練習で飛び込みは禁止されているためトラックスタートの練習ができないということもあって若い時から慣れ親しんだクラブスタートで通しています。
もし読者の皆さまが経験が浅いようであればこの方法によるスタートをお勧めします。理由は両足でしっかりとスタート台を蹴って入水エントリーができるので失敗が少ないと思います。
さてこのクラブスタートで飛び込む際に2種類の飛び込む方法がありますので紹介します。
それはスタート瞬間の腰の位置です。まず1種類目はスタート台のエッジをつかんで安定させますが、腰の位置が前で静止、号砲で素早く飛び込む方法と腰を目一杯引いて力をタメ、その反動を使って飛び込むという2種類があります。
でも2種類目の方法は反動という力があるのですが、身体の重心が後ろに下がるため、わずかですがタイムロスとなります。
1-1-2. トラックスタート(クラウチングスタート)
このスタート方法は陸上競技のスタート法から習ったスタートです。最近の公認プールではほとんどがスタート台にはバックパネルが設置されているためにこの片一方の足を後ろにして陸上トラック競技のようなスタートができるようになっています。
飛び込む瞬間に反動を使って強い瞬発力を生み出すために後足から前足へ流れるような力の移動によって強い初速度を得ようとするものです。
まず台上のバックパネルがないプールで日々泳がれているのであればほとんどトラックスタートの飛び込み練習はできないと思います。
このクラウチングスタートについては以下の記事を参照ください。
1-2. 水中スタート(参考)
参考までに飛び込めない人のためにマスターズ水泳競技会でも水中スタートは認められています。
長いホイッスルが鳴れば、速やかにプールの中に入り、一方の手でスターティンググリップを持ち両足を壁に付けてスタートの号砲を待ちましょう。
この水中スタートは一応認められてはいますが、読者の皆さまにはあくまでも飛び込みスタートを目指してレースに参加して欲しいと思います。
2. 上手になるコツ(飛び込み禁止の環境を吹き飛ばせ!)
シニアメンバーであればほとんどの所属プールでは「飛び込み禁止」と言う規則の制限があります。
この規制を克服し、飛び込み練習より大切な上手になるコツを解説したいと思います。
それには、飛び込みにかかるルールをしっかりと理解して自分の呼吸で集中!
他のレーンの選手に惑わされる事なく、スタート音にだけ集中して最高のスタートイメージを手に入れましょう。
そのためにもまずはルール、そして心構えが重要となります。
2-1. スタートルール
日本水泳連盟競泳競技規則(ルールブック)ではスタートに関して次のように記載されています。
出発合図の前にスタートした競技者は失格となる。失格が宣告される前に出発合図が発せられていた場合、競技は続行し、フォルススタートした競技者は競技終了後失格となる。出発合図の前に明らかにフォルススタートしたとみなされる場合は、出発合図はせず、その競技者を失格する。他の競技者については、元の位置に戻り再出発する。
このように規定されており、とても厳しいルールとなっています。
もっと詳しくは以下の記事を参考にしてください。
スタート台でバランスを崩して入水してしまうことも不安がよぎるかもしれませんが、ともかく落ち着いてスタート台に乗ってからはともかく静止してスタート音に集中しましょう。
さて、招集場スタッフから促され、自分のレースの順番がやってきました。自分のレーンを確認して、そのレーンコース台後方の席でスタートの準備をして待ちましょう。
短かい音のホイッスルが3回なります。この時選手は飛び込みスタート台のそばに接近します。スタート台に足をかける選手、一段高いプールのエッジに立つ選手、スタート台の後方で立っている選手と様々です。
次に長いホイッスルがなります。これで選手は全員飛び込みスタート台上に上がりスタートの号砲を待ちます。
スターターの「よーい」の掛け声が発せられます。ちなみに国際大会では(take your marks)が「よーい」の意味です。
それから結構早いタイミングで電子音によるスタート合図の号砲が鳴ります。この瞬間に飛び込むことになります。あとはもうガムシャラにゴール目指して泳ぐだけです。
2-2. スタートの心構えと注意点
前に述べたようにスタートの手順は極めてシンプルです。でも選手の緊張度は極限に達しています。この時に平常心で居られる選手が強い結果を残すこととなります。
飛び込むのは経験が浅いと本当にある種の恐怖心を覚えます。
したがって飛び込んだ感覚は違和感があります。深く入水しすぎて浮き上がりの不安などを感じることがあると思います。
2-2-1. 恐怖心を払拭させすコツ
競技会のプールはとても泳ぎやすく感じられると思います。冷やっと感じる水温そして深くて大きなプールです。
私などは競技プールでレースするのが楽しみです。こんなに泳ぎやすいプールで泳げる喜びがいつもあります。
・長いホイッスルが鳴ったら隣のレーンの選手にならってコース台に上がり深呼吸をして足指をしっかりかけて両手でスタート台を両手でしっかり握り身体を静止させ、スタート音にだけ集中しましょう。これが最大のコツです。
2-2-2. あとは身体に任せましょう
意識は遠くへ飛ぶ、そして「腹打ちでOK」と考えて思いっきり飛び込みます。しっかり飛ぶだけでナイススタートは間違いはありません。
勇気を出してこの経験ができる喜びに浸りましょう。
あとは体に任せて泳ぐだけです。競技が25mならもう考えている余裕もありません。ゴール目指してガムシャラです。スイミングキャップが飛んで行こうとゴーグルが外れようとそんなことは関係ありません。
2-2-3. 観客席での観察
観客席で同僚選手の応援をしている時に招集場からスタートまでの手順、そして飛び込むタイミング、長いホイッスルからスタートまでの間などをいろんな種類の競技をじっくりと観察して自分の番に備えましょう。
その観察の中で選手がスタート台で全員が静止してから号砲までの間合いについてスタート担当役員の癖がつかめられたらそれだけで恐怖心が払拭できます。
2-2-4. ゴーグルが外れることの防止策
レース経験が少ない選手でよく目にするトラブルケースにゴーグルが外れてしまう。また飛び込んだ衝撃でゴーグル内に水が入ってしまうなどです。
あまり強くベルトを締め付けると泳いでいて前方の視界が悪くなりますので試合前の公式スタート練習の時にチェックしておきましょう。
でも仮にゴーグルが外れても、水が侵入したとしても完全無視です。レース当日まで頑張ってきた記録のために無視して泳ぎましょう。
3. スタート経験こそ最大のコツ

まだまだ経験不足なマスターズスイマーにはレースの度に本番はもとより、開会式前のウオーミングが許される時間にウオーミングに加えて飛び込みスタート練習を繰り返すことが大切なコツといえるでしょう。
そしてスタートが上手になるコツはともかく経験値、練習の数だと考えて何度も繰り返しましょう。
短水路(25mプール)での大会ではサブプールでのウオーミングアップは認めてられていますが、スタート練習は開会式前の公式スタート練習がありますので各レーンで1人ずつレースに準じて行われますので必ず参加して経験を積みましょう。
そして公式練習前のウオーミングアップ時間にも1レーン、8レーンでは飛び込みスタートが許されていますのでレーンの安全を確認して飛び込みの練習をしましょう。
長水路(50mプール)では飛び込み競技用プールが併設されているケースが多く、ウオーミングアップは常時このプールで可能です。
そして併せて一番隅の1レーンが飛び込みスタート練習が許されている場合がありますので、このケースの場合には自分の競技レースに備えると同時に飛び込みスタートの上達に向けて恰好の練習チャンスです。積極的に活用しましょう。
詳しくは次の記事を参考にしてください。
では上手な飛び込みに必要なことはともかく何度も何度も練習して、本番レース経験を積んでいくしかありません。
スタート時の激しい緊張からスタート反応の遅れや、ゴーグルが外れたり、浮き上がりがうまくいかないなどの失敗も多々ありますが、これも良い経験です。
真摯に受け止めましょう。こうした失敗を繰り返すことで上手な飛び込みができるようになります。
でもレース当日まで頑張って練習してきたわけですからともかく全力を尽くしていればスタートも素晴らしい飛び込みができると思います。レースを楽しんで欲しいと思います。
可能であれば所属クラブで飛び込みスターもしっかりと指導してくれる恵まれた環境にあるスイマーであれば素直に指導者の指示に従って練習をして欲しいのですが、その環境にないスイマーにとって、スタートは本当に大きなハンディキャップです。
そのようなスイマーにとってはともかくレースエントリーを出来るだけ数多くするように記録会、地域でのレースなど日程を調整して出来るだけ多くのレースにエントリーしましょう。
4. まとめ
水泳の競技会を想定した飛び込みスタート練習に関してそのスタートの種類とその手順、上手になるためのコツなどについても述べきました。
私の若い頃にはスタート時に故意にフライングスタートをして確認チェックをするなどといった悪質な選手もいた時代も経験しています。でも最近ではスタートで失格になるケースはほとんど見たことがありません。それだけにルールが厳しくなっており、スタートは厳格です。
十分に練習できない環境にあり、どうしても後回しにされがちな飛び込み練習です。
私にとってはレース当日は大切なスタート練習でもあります。あらゆる機会を活用していろいろな種類の飛び込み練習を重ねてスタートの苦手意識を払拭しましょう。
最後に私の事を申し上げたいと思いますが、スタート台に立つ喜びというか最高の舞台に立てる幸福感が素晴らしい経験です。
もちろんレースの瞬間までの緊張感を考えますととても大きな重圧ですが、スタート台から飛び込む瞬間の歓びは素晴らしいものです。
どうかこの緊張感を嫌がらずに積極的に受け入れて喜びに変えていこうではありませんか、レースへの積極的な参加を呼び掛けておきたいと思います。
最後までお付き合いいただき心から感謝いたします。ありがとうございました。
なお、水泳に関して次の記事も興味深い内容となっていますので是非ご一読いただければ幸いです。





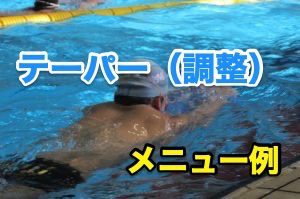



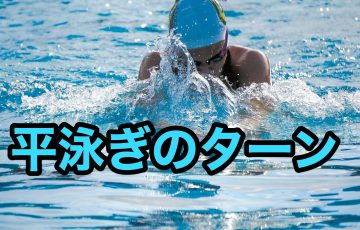

















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。