水泳経験の浅いビギナーが陥りやすい症状に酸欠症状があります。
そしてトップスイマーはこの酸素不足を逆に利用して泳力強化に取り組んでいる状況を紹介していきます。
究極結論的には水泳中、決して無理をしないこと、苦しくなる前に立ち止まって、深呼吸をしてあとは水中を歩きましょう!
さて、なんとか25mを泳ごうと必死にもがきながらやっとでたどり着いた25m、もう心臓も胸も破裂しそうな興奮状態です。
顔は青ざめて、もうあえぎがひどく呼吸さえままならないような状況にみえます。
これは言うまでもなく酸欠の症状といえるでしょう。
このケースでは僅か1分前後の短い時間内でのことですが、25mを泳ぎ切った人にとっては体力も使い切ってのことで、すぐには元の状況にはもどりません。
ゆっくりとなんども深呼吸をして、落ち着きを取り戻してもらわないといけません。これが何よりも大切なことですのでくれぐれも無理はしないようにしましょう。

目次
1. 水泳中の酸欠事例と症状
酸欠症状とはあまり考えたくない事例ですが呼吸が乱れ、かるい酸欠状態になるといったケースから、予期せぬ事態に陥って酸欠を原因とする生命の危機にさえ至るケースといろいろあると思います。
1-1. 一般的酸欠事例
ここでいろいろな症状による酸欠の事例についてまとめておきましょう。
1-1-1. 富士登山(筆者の酸欠体験事例)
まず私が富士登山中、経験した酸欠事例は7合目辺りから起こりました。
8合目にある山小屋で1泊する予定で気分爽快で軽快に5合目からの登山を開始したのですが、6合目を過ぎてから元気がなくなり7合目に差し掛かる頃にはもう1歩も前に足を出せないくらいのけだるさというか、軽い吐き気もあり、顔は青ざめて、典型的な高山病、酸欠症状となりました。
持参していた携帯用の酸素ボンベを2本使い、また友人のも借りてやっとのことで8合目の山小屋にたどり着いたのを今でも覚えています。
若い時には南アルプス縦走などの登山経験もあり、いつも水泳をしているからとタカをくくり、登山口から混雑をふりきるように追い抜いて歩いていました。
でも富士山はそんな生易しいものではありませんでした。
酸欠の辛さはすさまじかったですね。
いくら深呼吸をしてももとに戻らず吐き気に悩まされました。30分近く酸素吸入をして休憩しても歩きだせば直ぐにまた苦しくなってきたのは辛かったですね。
1-1-2. 朝、寝起きの悪い状態
朝の目覚めがスッキリせずにあくびばかり・・・
ということがよくあると思います。これは軽い脳の酸欠状態だと思います。
夜更かし、深酒など要因はいろいろあると思いますが、朝目覚めてあくびばかりというのは明らかに脳の酸欠と言えるでしょう。
従って、気持ちをリラックスさせて、深呼吸をしっかりするなど、英気を養う必要があります。
1-1-3. 過呼吸症状
急激なストレスなどにより、極度の呼吸が頻繁となり必要以上の換気活動によっておこる過呼吸の症状は、当初は酸欠に似た症状を起こします。
例えば胸が苦しくなり頭のふらつきなど寒気や耳鳴りなどをきたします。
この症状がよく起こるスポーツにはマラソンやサッカー、水泳など呼吸を頻繁にする運動中あるいは運動後に起こる可能性があります。
1-2. 水泳中の酸欠事例
水泳中に酸欠を起こすというのは最近はあまり耳にしませんが何と言っても子供達の溺水事故の事例が気になるところです。
1-2-1. 溺水事例
水泳の授業で泳力検定をしていて、小学生の男子がスタートから16m付近で「だるま浮き」状態で動かなくなっていた事例や、
また高校生女子がクロールと平泳ぎ練習を終えた直後に潜水練習に入ったところでうつ伏せになって溺水状態であった事例など
1-2-2. 中高年の水泳で起こる事例
頑張り屋さんの中高年の水泳愛好家にとって水泳はついつい無理をして泳いでしまいます。
25mまで何が何でもという意気込みでほとんど十分な呼吸ができない状態で泳ぎ切る場合がよくあります。
・頭痛
ついつい頭痛の症状が起きてしまいます。これは酸欠によるものなのかどうかは不明ですが、一時的な酸素不足は拭えません。
得てして血圧上昇による頭痛ではないかと思います。
・顔が青い
またよく似ているのですが、私がよく目にする光景なのですが、60歳以上のメンバーさんなのですが、ともかく息継ぎがうまくいかいないようで、何度も繰り返し25mをクロールで泳いでいらっしゃるメンバーさんをたまに見かけます。
25mを泳ぎ切ると、顔が青く、天を仰いでいらっしゃいます。
そしてたっぷりと休憩をしているのですが、顔色が戻りません。でも十分休憩と取れたと思うのでしょうかまた25mを目一杯泳がれます。
徐々にあくびが多くなって、ほとんど回復しないのかもしれません。そしてプールから上がられてしまいます。
こうしたケースは軽度ではあるのでしょうが酸欠症状だと言えると思います。
とアドバイスをするのですが、25mのこだわりがなかなか払拭できないでいらっしゃるようです。
・あくび
水泳中のあくびはあまり考えられません。
泳いだ後、休んでいるときにでるあくびは少し危険です。かなりの酸素不足が想定されると思います。
少しでも酸素を摂取しようとする身体内部からのサインだと思います。
1-2-3. ともかく無理は禁物
中高年世代にはどうしても我慢強いのでしょう!
25mの途中で止まる人は少ないです。言い換えれば25m泳げる自信のある人しか泳がないと言った方が良いかもしれません。
なのも恥ずかしいことではありません。練習のたびに少しずつ距離が伸びて行けばそれで十分です。
くれぐれも息をこらえて25mを泳ぎ切るというのは酸欠、血圧上昇の原因になりないも良いことではありません。
2. 具体的対処方法(決して無理をしない!)


水泳で酸欠症状というのは前章でも述べてきましたが、顔が青ざめる、天を仰ぐような息づかい、あくび、頭痛、吐き気などの症状があります。
原因はともかく、急激に激しい水泳によってもたらされます。
体調があまりよくないにも関わらず、ウオーミングアップ無しに一気に25mを全力で泳いだりしますと、人の身体の中では突然の運動でパニックに陥ってしまいます。
ではここで酸欠症状に陥ったら、どんな対応を取れば良いのでしょう。対処方法について述べたいと思います。
2-1. 吐き気、青ざめた顔
この症状に至ればプールで休憩していて返って危険です。身体は冷えてしまい、ますます結構がよくなく改善されません。
プールスタッフに任せて必要な処置が重要です。
もしご自分が吐き気をもよおしたら、もしくは誰か他のメンバーさんから「顔が真っ青ですよ!」などと言われたら速やかにプールスタッフに申し出る勇気を忘れないでください。
そしてメンバーさんの中で青い顔の人を見かけたら、同様の対応をとるように心がけてください。
2-2. 頭痛
この場合、きっと25mとか50mを急激に泳いだ後だと思いますので、出来るだけ深くて長い呼吸をして呼吸を整えましょう。
そして壁に持たれて休息をとっていても改善されませんから、ゆっくりと深呼吸をしながら歩きましょう。
25mをゆっくりと歩けば頭痛はかなり改善されると思います。もし一向に改善されないようであればプールスタッフに申し出ることを忘れないでください。
症状が深刻な状況に至っている可能性もあるのかもしれません。
もし急激な水泳による一時的な酸欠症状であったり、血圧上昇であるならば、歩くことでクールダウン効果となり、少し改善されるはずです。
そして後はもう泳がずに身体が元に戻るまでゆっくりと歩いて、プールにあればジャグジーやお風呂で身体をゆっくりとリラックスさせましょう。
2-3. あくびやあえぎ
25mを必死に泳いで天を仰いで喘ぐような息づかいや、軽いあくびが出るようなら、これは一時的な酸欠状態でしょう。
box class=”blue_box” title=”ポイント”]水分補給をして深呼吸、そして前の症状と同様に水中を歩いてクールダウンをしましょう。[/box]
これでかなり呼吸が普通に戻ると思います。
2-4. 常に心拍数のチェック
プールに入って泳ぎだす前、そして水泳途中の休息、水泳後と頻繁に心拍数を計測する癖をつけているといろんな面で役に立ちます。
心拍数の測定方法は手首や頚動脈に触れて脈拍を数えます。
6秒間の脈拍を3回くらい測って平均値の10倍が1分間の心拍数です。
私の場合ですと、起床時で60前後、普通時で70〜80、水泳後は80〜90です。
有酸素運動目的では130を目標に泳いでいます。
酸欠症状が出るような状況ではきっと心拍数は170以上も超える心拍数だと思います。
参考までに最大心拍数は220 − 年齢ですからそれ以上の心拍数にならないように水泳もコントロールが必要です。




3. 意図的な酸素不足下でのトレーニング


過去のオリンピック水泳で2種目2連覇の偉業を成し遂げた北島康介選手の高地トレーニングというのが当時話題となり最近においても類似するトレーニング合宿についてよく耳にします。
3-1. 高地トレーニング
また白血病で闘病中の池江璃花子選手の高地トレーニング中の不調で帰国後白血病と診断されました。
彼女の場合は高地トレーニング中に気分が悪いとか体調不良などの症状があったようですが、高地トレーニングに酸欠症状が加速されていたのではないでしょうか・・・
北島選手も池江選手も自由形1500mといった長距離選手ではありません。
北島選手は100m、200mの平泳ぎ、池江選手も50mや100mを得意とするスプリンターです。
こうしたスプリントアスリートの高地トレーニングというのは少し危険なような気がしてなりません。
マラソンランナーとかトライアスロンアスリートなら高地トレーニングはとても効果的だとは思いますが。
スプリンターにとってはどうなのでしょうか、不思議な気持ちがします。
とはいえ、池江選手は高地トレーニング中の不調で白血病を早期に発見できたことは幸運だっとファンの一人として不幸中の幸いと言わざるを得ません。
3-2. ノーブレッシングダッシュ
軽い酸欠状態を克服することによりより心肺能力を高めるトレーニング方法の是非はともかくとして私も学生時代にはノーブレッシングダッシュをよくやりました。
25mをノーブレでダッシュしてタイムをあげる練習や50m練習でラスト12.5mはノーブレゴールダッシュといった練習は日常的にやってきた練習でした。
でも高齢になった今、ノーブレなど恐ろしくてできません。
私もそうなのですが、水泳選手のスポーツ心臓というのは水泳に限ったことではありませんが、若い成長期におけるトレーニングによって心臓肥大となり場合があるようです。
私も心臓肥大で脈拍も途中で飛んだりする場合があったり毎年の心電図で精密検査を受けることもあるので今は無理な事はしないようにしています。
さてこのノーブレダッシュもある意味体内では当然ながら酸素不足をきたし無酸素に近い状態でダッシュをしているのです。身体に与えるダメージが無いとはいえません。
4. まとめ
水泳によって引き起こされる酸欠症状について、個人差もあり軽度の酸欠症状もあれば、深刻なケースもあります。
いろいろなケースを症状で分けて解説・検証をしてきました。参考にしていただいて無理のない水泳を心がけるようにお願いしたいところです。




心がけてほしいことをまとめて列挙いたしますとおおよそ以下のようになると思います。
・ウオーミングアップ・クールダウンはゆっくりと時間をかけて
・苦しくなる前に立ち止まって後は水中歩行
・こまめな水分補給は忘れない
・水泳前後の血圧測定、心拍数チェックは忘れない
・最大心拍数を超えないように
ともかく水泳は健康のための運動習慣であるのですから、無理のないように水泳を楽しんで欲しいと願いつつこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いいただき心から感謝しています。
なお、以下の記事もとても興味深く参考になると思いますので是非ご一読いただければ幸いです。










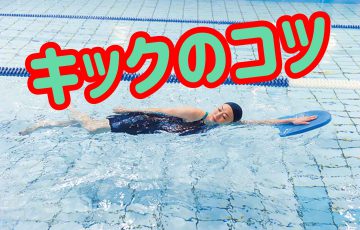














けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。