水泳の歴史を紐解くと古代ギリシャの時代にはすでに水泳が盛んであったことが記されています。きっとサバイバル的な水泳として発展をとげてきたのでしょう。
日本の水泳は「水術」「水練」とも呼ばれ甲冑をつけたまま視界を保ったまま泳ぐ技術や水中での格闘技術など武士の嗜みとしても現在に受け継がれており、この流れをくむ平泳ぎは日本のお家芸です。そして私自身も立ち泳ぎや横泳ぎなどは得意です。
健康的なスポーツやレジャーとして歴史的にも老若男女を問わず親しまれている水泳の楽しさが読者の皆様に伝わっていただければ幸いです。

サバイバル泳法として
立ち泳ぎを紹介します!常に一定の浮力を維持できる泳ぎ方
「巻き足」と言います平泳ぎのキックでは浮力を維持できません
でも巻き足は常に膝から下の足を右左交互に回転させる泳ぎ方です水深が肩まであれば十分練習できます
これも水泳ですhttps://t.co/6gKghc5r8e— 石原孝@水泳歴60年爺 (@hayaokitori) August 19, 2019
目次
1. 日本水泳の歴史を紐解く
1-1. 水泳の発祥
人間が泳げるようになった起源は資料がなくはっきりとはわかっていませんが、全ての哺乳類が泳げると言われていることから、人間としての活動が始まった頃にはすでに泳げていたのではないかと考えらえています。
それは地球上の70%が海に覆われており、陸上にも川や湖や川があり生活を営む上で水泳はなくてはならないものであったとことは十分にうかがい知れるところです。
そして度重なる水害からの逃れるため、あるいは移動のため川や池などを横断することも重要であったはずです。
歴史的な資料としてはおよそ9000年前に人が泳いでることを現す壁画があったと言われ、古代ギリシャでは水泳が盛んであったことを示す絵画や彫刻も発見されており、古代のギリシャ時代から水泳が盛んであったことがわかります。
そして狩をする、漁をするなどといった食料を得るために獲物を確保するに必要な手段であった訳で水泳も非常に重要であったことは自ずと理解ができます。
初期の泳ぎ方はその他の哺乳類と同様に犬かきのように視界を確保して手足を交互の動かせて泳いでいたことでしょう。そしてその泳ぎ方に改良がなされ平泳ぎに似たような泳ぎ方が起源であると言われています。
その後、人間の考えることですから、より速く、より遠くへ泳ぐために必要な泳ぎ方が生まれて後世に受け継がれてきたことは想像がつきます。
1-2. 競技水泳の発展
そして水泳は19世紀に入りイギリスで起こった産業革命以降、近代スポーツの発祥とともに陸上競技と同様に水泳競技として発展と遂げていったと考えられます。
さらに競技はプールでタイムを競う競技が一般的ですが、自然の中の水面を泳ぐオープンウオーターであったり、球技、飛び込み、シンクロナイズドスイミングなど多種多様な競技が普及されてきました。
一方では健康的なレジャーやレクレーションとしてビーチで日光浴も兼ねながら健康志向の強い楽しみとしてブルジョワを中心に広がっていったことでしょう。
そして現代においては水泳は健康的でとても有効な有酸素運動の代表格として普及してきているのです。
2. 武術から競技へ目覚ましい発展を遂げた近代日本水泳


日本における水泳の歴史は日本泳法もしくは古式泳法とも呼ばれて日本古来の泳ぎ方が確立しており、日本水泳連盟が公認する流派が13あります。
しかし日本における水泳の起源を考えれば世界の歴史が物語るように獲物を得る基本的な活動であったり、度々被る洪水などから身を守るためのサバイバルとして誰もが泳げる能力は得ていたと私は思います。
2-1. 武術として発展した水泳
日本における水泳の歴史上の特徴は武術としての発展の歴史が克明に記録されており、その泳ぎ方は「水術」「水練」「踏水術」「遊泳術」「泅水術」などが伝わっており、江戸時代の初期より400年の歴史を有していると言われています。
そして日本水泳連盟はこの日本泳法について連盟が認定する範士、教士、練士、游士、如士、和士、修士の7つの資格を設けているが現在一般のプールで練習をしており、イベントなどで古式ゆかしい甲冑を着て参加をしています。
こうした日本泳法は武術としての側面から隊列を組んだ遠泳や海や川での安全な遊泳、そして災害時のサバイバル泳法として発展してきたと考えられます。
従って競技水泳である4つの種目と比較すれば速さにおいては到底及ばず日本の競技水泳から姿を消してしまったのです。
でも規則上は今でも自由形においては日本泳法で泳いでも違反ではありませんが、敵うものではありません。
2-2. 日本泳法の継承
武術の一環として受け継がれている日本泳法は日本水泳連盟が認定する13の流派があり毎年春には日本泳法研究会が主催で競技会が開かれています。また日本水泳連盟主催でも毎年夏に開かれています。
競技会の内容は研究発表や実技披露などが主体ですが、個人種目としての競技も行われています。競技については6種目あって日本泳法競技規則でまとめられています。
内容は泳法競技、横泳ぎ競泳、支重競技、団体泳法競技など6種目あります。
また子供達には全員、6月には夏休み前に水辺での事故防止のため、洋服を着た状態で泳いで万が一の場合の指導を行う「着衣泳」の講習会があって現在の子供達にも日本泳法の一旦を経験することになっています。
2-3. 近代日本水泳の目覚ましい発展
筆者の私が水泳を始めたのは1960年代です。早いものでかれこれ60年を経過して半世紀以上を経験しています。
この間、水泳の歴史はどう変わっていったのか、泳法そのものは大きな違いはありませんが、
平泳ぎのルールは大きな変化を遂げました。私の専門種目が平泳ぎだったのでその変遷を私自身の経験として味わってきました。
そして日本の水泳界にも大きな歴史的な出来事としては水着の変遷があります。
さらに北島康介選手のオリンピック2種目2連覇、日本の選手が水の怪物の異名を持つマイケル・ヘルプスに匹敵する個人メドレーで世界にも通用するレベルに達する選手の台頭、また自由形短距離においてもあと一歩のところまできています。
これらの歴史的な出来事や快挙はこれからも日本の水泳における歴史の1ページとして語り継がれることでしょう。
2-3-1. 平泳ぎの変遷
私が学生時代の頃には平泳ぎのルールは頭の水没禁止規定があり、スタート・ターン以外のストローク中には頭の一部が水面上になければならず後頭部に水が流れる状態では水没と判定され失格となっていました。
そして私も何度か泳法違反になった苦い経験があります。
この頃の平泳ぎはナチュラルな平泳ぎで下半身が大きく上下動を伴いました。
その後1987年には水没禁止のルールが大きく緩和され、1ストローク毎に1回、頭が水上に出れば良いことになりました。
この緩和により上半身を水上に大きく出して落差を利用して推進力をえるウェーブ泳法が流行り、上半身の大きな動きで得られるウェーブにより腰の位置を高く保持しながら水中では下半身の上下動を最小限にするキックが主体となりました。
それからスタートとターンで水中での1かき1蹴りについてもドルフィンキック禁止の時代からドルフィンキックの使用についての緩和措置など段階的に大きな変更が行われてきました。
その変遷の中で水泳をやって来た私にはタイムの向上と失格との間でいつもレースには神経質でした。
このように水泳競技4種目の中で平泳ぎは歴史的な変遷を経て現在に至り、記録も大きく進歩して来ました。
2-3-2. 高速水着の登場
2007年の後半に突如として登場したSpeedo社のLZR Racer(レーザーレーサー)により記録の飛躍的進展がありました。
そして2008年夏、北京オリンピックではトップクラスの選手のほとんどはこのレーザーレーサーの着用により世界記録だけで23個が更新されました。
水着開発はしのぎを削り、水着開発競争が巻き起されました。
この状況は本来選手の実力を競う趣旨から逸脱しているとの指摘から2010年には水着のの規定が改正され国際水泳連盟(FINA)承認の水着が義務付けられるようになるなどの歴史的経過を経ています。




この水着規定の改正以降、北京オリンピック時に更新された世界記録は停滞をきたしたのですが、近年、逐一記録の更新がなされやっと本来の競技の趣旨に沿った記録となり高速水着の歴史は大きな問題を残しながらも大きな歴史的な出来事として私の記憶にもしっかりと残っています。
2-3-3. 和製ヘルプスの登場
日本の水泳の歴史に大きなインパクトを与えたアメリカの水の怪物との異名をもつマイケル・ヘルプスの存在は大きな意味を持っています。
ヘルプスはアテネ2004年から2016年のリオオリンピックまで活躍したアメリカの選手です。
オリンピック通算28個のメダルを獲得し世界選手権に至っては通算33個のメダルホルダーとして君臨しました。
その意味において日本水泳の歴史の中においても特出すべき出来事と言えると思います。
特に瀬戸大也選手は2019、韓国光州で行われた世界水泳2冠に輝き2020東京オリンピックの最有力選手として期待されています。
2-3-4. 自由形短距離の成長
自由形は近年、とても世界に通用しないとされる種目でした。
そして自由形のリレー種目においても決勝に残れる実力を得て、日本の自由形陣の活躍が期待されています。
この自由形が世界に通用するレベルに達しつつあることは日本水泳の歴史的快挙と言えるでしょう。
3. 是非習得して欲しい泳ぎ方


さて日本古来からの日本泳法の中でサバイバル泳法の意味からも、レジャーの観点からもぜひ習得してほしい2つの泳ぎ方をここで紹介したいと思います。
それは立ち泳ぎと横泳ぎです。
どちらも泳ぎ方の動画を私のツイッターで発信していますので見ていただいてイメージを頭の片隅に置いていただけたら幸いです。
3-1. 立ち泳ぎ
サバイバル泳法として
立ち泳ぎを紹介します!常に一定の浮力を維持できる泳ぎ方
「巻き足」と言います平泳ぎのキックでは浮力を維持できません
でも巻き足は常に膝から下の足を右左交互に回転させる泳ぎ方です水深が肩まであれば十分練習できます
これも水泳ですhttps://t.co/6gKghc5r8e— 石原孝@水泳歴60年爺 (@hayaokitori) August 19, 2019
私はこの立ち泳ぎ(巻き足)が得意です。なぜかというと学生時代水球の競技にも出場経験があり私は平泳ぎでしたからキーパーを任されていました。
深い飛び込みプールでキーパーの役目は寒さに耐えて立ち泳ぎでゴールを守るのが役目でした。
競技会では強いチームとやるときは立ち泳ぎからボールのインゴールを防ぐジャンプと立ち泳ぎの繰り返し、最大ジャンプでおへそが見えるくらいの水中ジャンプ力がありました。
そして弱い格下のチームとの試合では常にゴール前で立ち泳ぎで寒さに耐えていました。
このキーパーに基礎練習は立ち泳ぎ、巻き足です。両手に5kのダンベルを持っての立ち泳ぎは悲惨な練習でしたがよく耐えたものです。
足を交互に巻きながら浮力を安定的に維持する日本泳法の基本的な泳ぎ方です。
3-2. 横泳ぎ
横泳ぎは常に視界が確保されており
疲れずに長い時間
長い距離を泳ぐことができます。両足を挟んで得た強い推進力を
真っ直ぐ伸びた腕で維持もう一方の腕でも推進力を生み出す
とっても合理的な横泳ぎ…!サバイバルな泳ぎ方として覚えておくと良いと思います。https://t.co/XGEesnqNN8
— 石原孝@水泳歴60年爺 (@hayaokitori) August 21, 2019
この横泳ぎは水泳の泳法では最も楽で安心感のある泳ぎ方だと思います。それでいて長い時間の遊泳に相応しく、長い距離にも対応できる泳ぎ方です。




4種目の泳ぎ方を習得し、立ち泳ぎと横泳ぎが習得できればサバイバル泳法とすれば完璧でしょう。
4. まとめ
以上日本における水泳の歴史について私にとっても忘れられない歴史的な出来事もふんだんに織り交ぜて述べて来ました。
お楽しみいただけたでしょうか!
日本水泳の歴史は諸外国の場合と少し違っており、武術としての変遷を遂げました。
それだけに日本は水の豊富な国だったのでしょう。
お城を守るのもお堀があり、国を守るにも、攻めるも水を克服する必要があったのでしょう。
さて、2021年は東京オリンピックが開催されました。そして日本選手のめざましい活躍がありました。
過去水泳日本を支えた黄金時代の歴史をもつ日本でしたが、体格に恵まれない日本にとってはどうしても低水準にならざるを得ず今日に至っておりますが、最近の日本水泳界の活躍は台頭目覚ましく数多くの五輪メダリストも輩出しています。
また新しい日本水泳の歴史が刻まれることでしょう。
水泳の歴史は何も競技だけではなく、楽しみや健康のための水泳であったことは歴史的にも納得のいくところです。
日本の津々浦々ではいつも水泳は庶民と一緒にあった楽しみです。ヨーロッパのように一部ブルジョアだけのものであったのではありません。この日本人全ての国民が水泳とともに生きて来たことでしょう。
そして忘れてはならない、この水との関わりは水の災害国であるがゆえに水とともに生きて来た歴史があるのです。
これからも日本人ととって水泳が健康スポーツとして未来永劫親しまれるよう願ってこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いいただき心から感謝しています。ありがとうございました。
なお、以下の関連記事もとても興味深い内容となっていますのでご一読いただけたら幸いです。

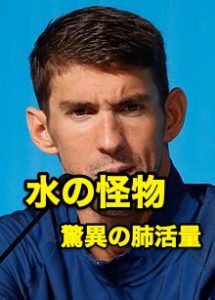






















けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。