水泳は有酸素運動の代表格としてよく知られていますが、海女さんは無酸素運動で泳いでいるのでしょうか・・・?
そもそも有酸素運動と無酸素運動の違いはどういうことなのか?
また併せて、経験や泳力レベル別にこの点をより掘り下げて解説していきたいと思います。
水泳をしている人は全くの初心者であったり、ダイエット目的であったり、競技会を目指して頑張っている人であるなどそのレベルも様々です。
そのレベルにあったアドバイスをこの記事で伝えていこうと考えていますので、水泳を正しく理解されて楽しく泳いで欲しいと思います。
また「無酸素運動」という表現そのものに誤解を招く恐れがあり適切ではないように考える筆者の私見も述べていきたいと思いっます。

目次
1. 水泳における有酸素運動と無酸素運動の違い
1-1. 定義
有酸素運動、無酸素運動とは以下のようにwikipediaでは定義されています。
有酸素運動とは好気的代謝によってヘモグロビンを得るため長時間継続可能な軽度または中程度の負荷の運動をいう。
それに対し、無酸素運動とは嫌気的代謝によって酸素の供給がひっ迫した状態でも一時的にエネルギーを得る高負荷な運動をいう。
ただし体内に蓄積した嫌気的代謝の生成物である乳酸は有酸素運動と同じくTCA回路で代謝されるので結果的には同じ代謝である。
(TCA回路とはクエン酸回路で好気的代謝に関する最も重要な生化学反応回路であり、酸素呼吸を行う生物全般に見られる) Wikipediaより
1-2. 有酸素運動と無酸素運動の違い
また別の言い方をすれば、ある程度の時間を継続して行う運動は有酸素運動であり、短距離競技のような運動を無酸素運動と便宜的に区別していることが多く、
でも多くの運動の場合、有酸素運動と無酸素運動が共存するなかで両方の要素を持ちながら運動しているのが水泳の特徴です。
1-3. エネルギー発生の仕組み
まず有酸素系ではグリコーゲンやグルコースといった糖分や乳酸、脂肪を酸素と共に燃焼させてエネルギーを生み出し、
乳酸系ではグリコーゲンがピルビン酸を経て乳酸に分解される過程でエネルギーを発生させるため、激しい無酸素運動により活発となる
リン酸系ではクレアチンリン酸の分解によりエネルギーを発生させるため最高の運動強度を維持できるのは10数秒程度と極めて瞬間的なパワーのエネルギーであるとされています。
1-4. 水泳は有酸素運動なのか
では水泳は有酸素運動なのか、無酸素運動なのかですが、
水泳経験の少ない人が息をこらえて泳ぐ場合や、素潜りの海女が海底での作業などは無酸素運動で、しっかりと呼吸のタイミングよく泳ぐ人が有酸素運動なのかというとそれはちょっと意味が違います。
すなわち前章で述べたようにエネルギー発生の仕組みが有酸素・無酸素運動ではまるで違います。
そして無酸素運動になるとすれば短時間に爆発的なスピードを必要とする25m、50m競泳などを指すと言えます。
そしてゴール前のラストスパートにエネルギー発生を無酸素運動に切り替えて全力力泳をする場合に該当するのでしょう。

1-4-1. 水泳は効率的な有酸素運動
水泳はとても効率的な有酸素運動であることは疑いのないところです。
でも水泳経験が少ないビギナーにとって一番の課題は息づぎでしょう。この息継ぎがタイミングよく行われてスムーズなペースで長い距離を泳げるようになってはじめて有酸素運動の効果が期待できるのです。
もし足がつるなどといった不足の事態が起こるのであればそれは無酸素運動のエネルギー燃焼で乳酸が発生し蓄積されたのだと想定されます。
でも基本的に水泳のエネルギー燃焼メカニズムは有酸素系ですから25m泳ぎ切った時には有酸素系と乳酸系の無酸素運動が重なったエネルギー燃焼が行われるとも考えられます。
そして25を泳ぎ切った後の呼吸を整える間の休憩で有酸素運動が停止状態となり、有酸素運動効果は中断されるでしょう。
1-4-2. 水泳における無酸素運動
陸上競技で言えば100m走や投てき種目やジャンプ競技などの爆発的な瞬発力を必要とする競技に該当するでしょう。
水泳競技の場合における無酸素運動とは、最も短い競技種目である25、50mでしょう。
そして選手はそのレースで自己ベストを目指して日頃の練習から、無酸素運動による瞬発力を効果的に発動できるように練習することになります。
でも100m以上の競技になると1分近くの運動時間が必要となるために有酸素運動と無酸素運動を効率的に組み合わせ、エネルギー燃焼システムを変えながら泳いでいることになります。
いつも有酸素運動系の練習ばかりしていると瞬発力が得られる無酸素運動への切り替えができなくなるため、自己ベストの更新は難しくなるでしょう。
ただ、私のようにシニアになると無酸素運動による筋肉や関節を痛めるといったリスクを考えるとどうしても無酸素運動系の練習を怠る結果となり、瞬発力を要求するのはとても難しくなってきます。
1-4-3. ビギナーにとっての有酸素運動
まず息継ぎの練習を行うことによって無呼吸で泳ぐなどといった無理なことはやめて、息が苦しくなったら、そこからはウオーキングに切り替えましょう。
歩きながら呼吸をととのえ、また泳ぎ出すといった連続運動が有酸素運動を維持するに合理的といえます。
そして泳げる距離を少しずつ伸ばしていく考え方が最も適切だと考えます。
2. 泳力レベル別の考え方とポイント

前章まで、水泳の運動についてエネルギー燃焼のメカニズムから有酸素系、乳酸系、リン酸系の3つのパターンから有酸素運動と無酸素運動の原理をお話ししてきました。
でも水泳に取り組んでいる方々に泳力レベル別に考え方とポイントを詳しく解説していいます。
2-1. ビギナー
ではまず水泳経験の浅い水泳者に対するアドバイスです。それは有酸素運動系の水泳を心がけましょう。
2-1-1. 酸欠は厳禁
酸欠になりそうな場合は得てしてがむしゃらとなり、無酸素運動のエネルギー燃焼にスイッチされ乳酸が蓄積されることになります。
苦しくなったらそこで止まる、そして壁まで呼吸を整えながら歩きます。それから歩行レーンに移動して25もしくは50m歩いて呼吸を整えましょう。
呼吸が戻るまではいくら歩いてもかまいません。その上でまた泳ぐというエクササイズを心がけましょう。
そして少しでも泳ぐ距離が伸びるように無理のない範囲で頑張りましょう。
距離が少しずつ伸びるのはとても楽しいものだと思います。
2-1-2. ターンサイドは休憩するところではない
なんとかターンサイドまで頑張って泳ごうと、その気持ちはとても素晴らしいことですが、ターンサイド到着後はどうしても休憩となり、運動が停止されてしまいます。
言い方を変えれば有酸素運動が停止され運動効果がその時点でストップします。
そうすると運動効果はそのターンサイドでの休憩で停止され、エネルギー燃焼効率も心肺能力の向上にもつながらず、その距離が一向に伸びてきません。
もっと言えばターンさえすれば泳ぐ必要などありません。
壁を蹴って水中姿勢をとるだけで結構ですからその上で止まりましょう。そして1ストロークでも伸ばしていきましょう。
2-2. 中級水泳者
クロールで200mくらいは泳げるようになった水泳者を中級レベルとしましょう。
2-2-1. 距離を伸ばすもしくはラップを短縮
もし時間的な制約があるのでしたら、200mで構いません。50mのラップを1秒でも2秒でも短縮して200mを泳ぎましょう。
そうすることで心肺能力はより一層向上してきます。とは言っても有酸素運動には変わりなく運動強度が高くなることで効果を得る時間が短縮されます。
2-2-2. 新しい泳法にトライ
クロールで100~200mも泳げるようになってもすぐに新しい泳法に挑戦するのではなくクロールでせめて400mくらい泳げるようになりましょう。
400mも泳げるようになれば相当に心肺能力も向上してきていると思います。
その上で新しい泳法にトライしましょう。
そして背泳ぎで100mも泳げるようになれば次は平泳ぎ、そしてバタフライを新しい泳法にトライすることでまた楽しさが増していきます。
でも100mくらいのクロールで直ぐに新しい泳法を覚えようとしてもなかなか思うように泳げないのが実情です。
それは泳ぐための心肺能力が十分でなかったり、水泳の基本である水中姿勢がまた未熟なため新しい泳法にトライしてもなかなか思うようにいきません。
勢いネガティブな感情が先行して水泳が楽しくなくなってしまいます。
2-2-3. 個人メドレーにトライ
そして4つの泳法ができるようになったら25mずつ泳法を変える個人メドレーにトライしましょう。
この場合、バタフライはストロークがマスターできずスイムでバタフライができなくてもドルフィンキックだけのグライドキックもしくはプルは平泳ぎのドル平でもOKです。
クロール、背泳ぎ、平泳ぎがマスター出来たら果敢に挑戦してみましょう。
2-3. 上級水泳者

次に地域の競技会やマスターズ水泳を目指している水泳者に対してのアドバイスです。
2-3-1. 無酸素運動系の練習をメニューにいれる
日々の練習に無酸素運動系の練習を一日に数回は入れて瞬発力を高めるスピード練習を取り入れましょう。
練習の基本は泳力を高めるスタミナ練習となりますが、これだけではスピードは高まりません。
水泳競技種目にもよりますが、短い距離のレースではスピード練習を取り入れなければ自己ベストの更新は望めないと思います。
2-3-2. 練習メニューの一例
25mダッシュ(インターバル15秒~30秒)制限タイムは自己ベスト、もしくは当該年ベストタイム
自己ベストが制限タイムですから毎回ベストを出さなければなりません。もし1本目に自己ベスト更新となれば2本目は1本目が制限タイムです。
この練習は無酸素運動系の練習となります。
たぶん自己ベストもしくは当該ベストを練習で更新するのは極めて難しいと思います。
でもこの練習を10本もすればスピード練習としてもスタミナ練習としてもとても効果的なスピード練習になることと思います。
25mをノーブレッシングで泳げなければ無酸素運動系の燃焼転換はとても望めません。
2-4. ダイエット目的者
水泳と水中ウオーキングを上手に折ませて、30分から40分は運動の停止がないように頑張りましょう。
これまさに有酸素運動効果の非常に高いエクササイズと言えるでしょう。
水中では水の抵抗があって陸上運動とは比較にならないエネルギー消費が得られます。
2-5. 共通するポイント
そしてシニアや上級者の水泳者には筋肉や各関節の故障というリスクも抱えていますので、十分なアップ・ダウンに努めましょう。
練習後、ジャグジーやお風呂でのセルフマッサージも配慮すれば翌日の筋肉疲労は避けられるでしょう。
3. 無酸素運動という表現は好ましくないのでは!

水泳に関して水泳は有酸素運動の代表格であると一般的に誰もが知るところです。
でも水泳は呼吸が自由にできないことから息をこらえて泳ぐとそれは無酸素運動だとよく言われます。
もちろん有酸素運動から無酸素運動に切り替えるために呼吸をしないノーブレッシングという手段は必要だと私は考えますが、そもそも無酸素運動という表現時代に誤解を生むのではないでしょうか・・・
言い換えれば有酸素運動であるかないかと言う表現の方が好ましいのではないのか!
そんなふうに思ったりもしています。
海女さんがサザエやアワビを獲る作業などは決して無酸素運動ではありません。
また溺れかかった人が必死にもがいているのはきっと無酸素運動系だと思うのです。そして水泳経験の少ない人が25mまでもう少し、必死にクロールをしている状況も無酸素運動系に違いありません。
アスリートの水泳選手がゴール前10mを無酸素運動系に切り替えられるかどうかで記録更新が可能になるのかもしれません。
このような観点から私は無酸素運動という表現をあまりしない方が賢明ではないかと思っています。
4. まとめ

以上、水泳を例にとって有酸素運動と無酸素運動について詳しくお話をすると同時にエネルギーの燃焼の仕組みを検証してまいりました。
冒頭の定義にもあるように有酸素運動では糖質や脂肪が酸素とともに消費され、無酸素運動は酸素を必要とせずにエネルギーを得るということでこれら両者はお互い共存する中で上手く連携しながら効率よくエネルギーを燃焼しながら水泳という運動をおこなっていると言えます。
シニア世代になってどうしても運動不足になりがちとなり摂取カロリーオーバーとなる昨今、水泳という非日常的な環境のなかで楽しく運動することが健康に素晴らしい効果を生むのではないかと私は考えています。
昔のような農作業や不便な家事作業などをしていた時代には運動不足などといった状況には至らなかったと思います。
でも近年の便利快適な生活の中ではなにがしかの運動は必須となっています。
そんな生活環境が激変する中で、水泳という有酸素運動は短時間で陸上運動以上のエネルギー消費効果が期待できます。
酸素を十分に消費するエネルギーの燃焼システムが働きますから、身体内部にもあまり悪影響を及ぼすこともないでしょう。
また泳ぐことで呼吸筋が鍛えられ、心肺能力の向上や循環器系も円滑に働き、高齢になっても健康を維持することができるように思います。
平均寿命が延びたと言っても健康寿命年齢の拡大につなげるためにはなにがしかの運動に見合う生活習慣が必要だと思います。
毎日30分でも1時間でもウオーキングでもいいでしょう。また一日おきにでもプールに行って水泳もとても楽しいと思います。
シニア世代にはこれからも健康でいきいきと残された人生を楽しく過ごしてゆかれるために、是非水泳の運動習慣を身につけらることを期待して、この記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いをいただき心から感謝しています。ありがとうございました。
なお、水泳関連記事に以下の記事もとても興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。


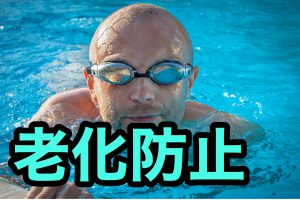









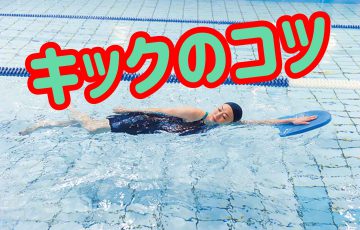











けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。