近年真夏の気候は酷暑ともいうべき災害級レベルの暑さが連日続くような状況が毎年続いています。
プールでは学校でも一般のレジャープールでも熱中症リスクのため授業・営業を休止する施設も現れ、社会問題にもなっています。
外気温の上昇に加えて運動などの活動によって体温上昇が起こりますが人の身体は自律神経の働きによって体温調整機能が働き発汗などによって熱を放射して体内の温度を下げる働きが備わっています。
しかし異常時には自律神経のバランスが崩れてこの体温調整機能が麻痺することで体内に熱が滞り熱中症に至るわけですが、幼児や高齢者、体調のよくない人、運動経験の少ない人にはこのバランス機能がうまく働きません。
水泳授業においては熱中症対策としてどのようなことが検討されているのか、また水泳時における熱中症対策としてどのような課題があるのか、ご一緒に考えて行きましょう。

目次
1 学校での水泳授業事情


まず学校における水泳授業現場での熱中症の実態を見てみましょう。
学校での熱中症発生事例
・年度別
| 年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 計 |
| 小学校 | 27 | 12 | 24 | 18 | 16 | 97 |
| 中学校 | 23 | 19 | 14 | 14 | 12 | 82 |
| 計 | 50 | 31 | 38 | 32 | 28 | 179 |
・熱中症発生場所
| 水泳中 | プールサイド | 更衣室 | 活動終了後 | 計 | |
| 件数 | 92 | 60 | 9 | 18 | 179 |
・活動別
| 体育授業 | 水泳指導 | 部活動 | 競技大会 | その他 | 計 | |
| 小学校 | 60 | 16 | ー | 8 | 13 | 97 |
| 中学校 | 47 | 1 | 34 | ー | ー | 82 |
・発生事例
・体育の授業中にプールで25mをクロールで泳いだ後、脱力状態となった(小5女子) ・プール清掃をしていた際、頭が痛くなってきたが大丈夫と思いそのまま下校し、帰宅後頭痛がひどくなり、吐き気も出てきた(小6男子) ・水泳の授業を見学していたが、日陰がなかったため気分が悪くなった(中2女子)
引用:いずれも独立行政法人日本スポーツ振興センター「学校屋外プールにおける熱中症対策」
日本スポーツ振興センターの調査結果では上記のようにプールでの熱中症発生事例が報告されています。しかしこの報告は2013〜2017年の5年間の調査で、以後の状況はさらに件数が増加していることが予想されます。
プールの現状
学校敷地内におけるプールの位置は一般的に日当たりがよい場所であり、直射日光を遮る物が無い場合が多く、プールは水深が浅く、炎天下では水温上昇が顕著で連日30℃を超えていると考えられます。
一方プール施設にはプールサイド、更衣室などがあり、この場所も熱中症リスクが水の中よりも危険と言えるでしょう。
2 炎天下での水泳授業の配慮
私自身、子供の頃の記憶をたどれば、水泳授業というのは蒸し暑い教室から解放されていっ時涼を感じ取れる最高の場所であり、楽しい時間でした。
夏休みにのプールは一般解放されていてPTAの父兄が交代で監視を務めて私のように水泳が大好きな子供は1日中プールで遊んでいたものです。
そして身体は真っ黒に日焼けして新学期には決まって黑ンボ大会があっていつも上位でした。
こんな楽しい思い出がありますが、その当時に風景を記憶にたどると、プールサイドには運動会用のテントを並べて、子供達は水泳に疲れればそのテント内で横になっていたものです。
監視員はPTAに加えて複数の先生、そして当番制の最上級生が監視に駆り出されていたように記憶しています。
水泳の部活動を始めた頃の記憶にはプールの維持管理は水泳部が担っていたように思います。
プールサイドにある水道の全ての蛇口からはホースで水道水をプール内に引き込み、水道水の使いすぎだとよく叱られたのを覚えています。
その当時、熱中症などという病気を知らなかったですが、案外知恵があったのかもしれません。
さて水泳の授業を考える場合にプール内での水泳だけの問題ではなく日常の健康管理、更衣室の環境、授業後のフォローまで考えなくてはなりません。


プール現場の対策
プールを使用しない日中にはシートで水面を覆い水温上昇を防いだり、授業中には可能な限り換水を行い水温上昇を防ぐ。
またプールサイドにはテントを張り、適宜散水をするなど直射日光を避け、プールサイドの放射熱を促進させる。
更衣室の対策
真夏の更衣室は高温多湿が想定されますので、換気を良くする為の工夫、例えば扇風機の使用や授業の無い場合も開放する。また一度に多くの生徒が利用しないように配慮するなど、また更衣場所をプールに近い涼しい教室に変更するなどの配慮が必要でしょう。
授業では入れ替えのタイミングには更衣室も混雑が予想されますので、より一層の配慮が必要となると思います。
授業の内容
水泳の授業では小学校、中学校、高等学校とそれぞれの学習指導要領の体育、保健体育の「水泳系および水泳」のねらいや内容を踏まえた指導がなされていると思います。
水泳指導と併せて水泳での安全指導を十分熟知されて指導に当たるとともに生徒自身の健康管理・安全管理をチェックできる能力を身につけられるような指導が望まれます。
特に熱中症に絞れば以下のようなことが考えられます。
・熱中症予防とセルフチェック
熱中症とはどういうものなのか、どういう症状が現れたら危険なのか、子供達に十分理解させておく必要があります。
自分の体調の変化を素直に友達や先生に伝えらえる能力がある子供は良いのですが、なかなか自分の体調の変化に気づけない場合や、気付きながらも伝えられない子供も多いと思います。
・グループでの行動
熱中症に限らず、単独行動をさせることなく、グループでの統率が重要でしょう。
中でも人員確認は随時行わなければならいでしょう。そして能力レベルに応じた水泳を考慮しながらも子供には頑張り過ぎないように、苦しくなる前に立ち止まるよう徹底すべきでしょう。
・適切な時間配分
先ほどと同様に能力レベルに併せて休憩との時間配分も考えましょう。予定していたメニューに依らなくても子供の状態を見て水から上がらせ休憩をとる配慮も徹底させるべきです。
また、プールに入水している時間を適切に配分して、効率的な授業の運営が必要でしょう。
・準備体操、整理体操の徹底
水泳前の準備体操や事後の整理体操はいうまでもないことですが、そのタイミングで生徒の顔色や仕草を十分チェックして生徒の変化を気づけるようにしたいものです。
水泳後の整理体操では気分が悪いとか顔色が良くない子供には要注意で監視を怠らないような配慮が必要です。
3 生徒だけでなく先生・スタッフのリスク回避
それから水泳授業中の熱中症対策となるとどうしても子供に目が行きやすいですが、
常にプールサイドに長時間滞在して過酷な環境の中で子供に神経を集中をしています。ついつい、自分自身の管理がおろそかになりやすいと思います。
また水泳指導をする教員は浅いプールで下半身は水の中、上半身は暑い直射日光を浴びています。そして実技で模範も示さなければなりません。身体の上半身と水中の下半身では体温さも相当なものです。
この状況で体調の変化があるのはむしろ当たり前と言えます。
水泳指導に当たるスタッフは単独ということのないように配慮して指導者もグループでつとめて、まず指導スタッフ自身の熱中症対策を忘れないようにすべきです。
上半身は直射日光を避けるような水着の着用やプールサイドには水分補給用の準備を怠らないようにしておくことが必要でしょう。
そして万が一体調不良の自覚症状を感じ取った場合の対応を事前に十分、検討しておき、授業に影響を与えないような配慮を整えておく必要があります。
得てして、子供、授業ファーストで準備がなされるため、教員の健康管理は後回しになるケースが多いと思いますので、指導者サイドの熱中症対策も忘れずに整備しておきましょう。
4 更衣室などの環境
繰り返しになりますが、今一度、更衣室の環境について述べておきましょう。
水泳の授業は学年ごとや複数のクラスが合同でプールで行われると思います。その場合、前の授業の終了と次の授業の開始が休憩時間でバッティングする場合があると思います。
このバッティングを防ぐ授業の時間配分がまず基本となります。
その上で、更衣室の環境の問題を考えねばなりません。
水泳の授業がある日には朝から更衣室の窓は全開にし風通しを良くしておく必要があります。
また雨天、曇天の場合にも湿度が高く不快な環境にある更衣室ですから風通しの配慮は無視できません。
更衣室はプール施設の下層部分に位置することが多いと思いますが、この更衣室にこだわることなく、別途教室や会議室を更衣室として使用する検討も必要かもしれません。
プール施設の下層部分は好天時でも湿度の高い環境ですから、風通しが良くなく、高い気温の場合には相当の室温になります。
そして大型工事用の扇風機の設置や、エアコンの設置なども予算に照らして整備が必要と考えます。そして今後に向けた予算要求も必要でしょう。
それから熱中症とは少し違いますが、その他衛生管理も十分に徹底させるよにしましょう。特にタオル類の共用は決してやらないように徹底しておきましょう。
5 その他水泳授業での配慮
その他考えられる水泳授業で配慮すべき事項として2点だけ重複するかもしれませんが重要なことでもありますのでここで述べておきたいと思います。


水分補給の徹底
学校側として準備する水分補給設備の設置、あるいは配布など、酷暑の中での水泳授業についてはできうる限りの配慮が必要だと思います。
プールの中での水泳練習だからと安易に考えるのは危険です。酷暑の日中には表面水温が30℃を超え32℃以上のお湯のように暖かく感じる場合させあります。
この高水温の状況で水泳を行えば発汗量も水温27℃の時の倍にも達する場合があります。勢い摂取する水分量を超える発汗量となり、脱水症状は免れません。
水泳授業は得てして顔を水につけているために喉の渇きが鈍感です。もし授業中に喉が渇いたような場合にはもうかなりの脱水症状に至っている危険性があります。
従って、気がつけば水分補給をするというクセづけを子供達も指導にあたる先生スタッフも同様にくれぐれも気をつけなければなりません。
見学者の配慮
それから体調が悪くて見学というケースがあると思いますが、プールサイドでの見学はとても危険です。かえって体調が悪化する場合も考えられます。
本来見学が必要なのかも含めて事前の検討が必要でしょう。
6 まとめ
近年、酷暑の異常気象が続く中で真っ黒に日焼けした子供達を見かける機会が少なくなったのでは!と感じています。
プール施設での子供達に対する熱中症対策も充実して生きている結果ではないかとは思いますが、今一度この記事で整理してまとめさせていただきました。
私の学生時代には35℃の気温というのは経験がありません。それに街中には今ほどアスファルトも整備されておらず、朝夕は涼しく、日中でも日陰に入ると涼しく感じる環境がありました。
校庭の脇に設置されているプールの背後には決まって樹木があって自然の日陰がありました。
でも近年は全くの炎天下のプールというのが学校現場では多いのではないでしょうか!

今回は熱中症に焦点を絞って述べてきました。酷暑の時期には高温注意報や警報が出る日が多くなります。この状況はある意味災害を意味する天候と理解する判断も必要なのかもしれません。
楽しい水泳授業であったり、いっときの涼を得られる癒しの授業も時と場合においては障害の起こりうるリスクを抱えており、学校側の対応も苦労が耐えないとは思います。
くれぐれも熱中症事故の無いよう心から願ってこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いをいただき、心から感謝しています。ありがとうございました。
なお、以下の記事も関連記事として興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。












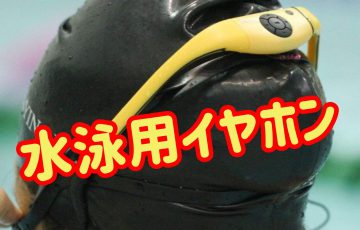











けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。