2019年、韓国光州で開催された世界水泳において日本女子水泳界のエース大橋悠依選手、女子200m個人メドレーでまさかの失格!
この失格の根拠はどうだったのでしょう。どのようなルール違反があったのでしょうか?
日本水泳連盟が確認をしたところ、背泳ぎから平泳ぎにターンを行った時にドルフィンキックを2回打ったということだったようです。
ルール上は1回となっており、大橋選手にとって、この2回ドルフィンはとても不本意なこと!
多分彼女自身そんな意識はまるでなかったはずです。
私もこのレースはテレビでしっかりと見ておりとても衝撃を受けました。
失格は今までの辛い練習が全て台無しになってしまいます。選手自身は故意にルール違反を起こした意識はなくても審判員の目にそう映れば失格となってしまいます。
私の経験から、失格に対する心構えなどについても述べていきたいと思います。

目次
1. 水泳競技ルール違反による失格
水泳競技のルールは(公財)日本水泳連盟が定める競泳競技規則により定められています。
このルールはもちろん国際水泳連盟(FINA)が定める競泳競技規則にのっとって制定されているために国際基準によるものです。
この規則の全文は以下を参照してください。
それからマスターズ水泳大会は各地域で開催される水泳競技大会においてはそのローカルルールが定められていますのでそのルールも十分に熟知して競技に臨まなければなりません。
では基本的なルールに従って、失格の可能性のあるような部分を抜粋して解説していきます。
1-1. スタート
言わずもがなですが、スタート合図の前にスタートした場合は失格となります。
私が学生時代にはフライングは3回認められていたので故意にフライングを行う選手さえいました。
でも今はこのスタートも厳格となりフライングで失格となるケースはほとんど見なくなりました。
1-2. 自由形(フリー)
自由形はどのような泳法でも良いとされておりますが、リレー種目、メドレー種目においては背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ以外の泳法でなければなりません。
この自由形において失格要素はほとんどありませんが、ただ一つどの種目ともに共通するスタートターン時の水没距離は15mと定められています。
1-3. 背泳ぎ(バック)
競技中スタート・ターン・ゴールを除いては体の一部が水面上に出ていなければなりません。
そして自由形同様にスタート・ターンの水没許容は15mとなっています。
ターン動作は体の一部が壁にタッチしなければならず、またクロールのクイックターンが認められており、片腕もしくは同時の両腕の一かきが認められ、足が離れる時には仰向けの姿勢でなければなりません。
ゴールタッチでは仰向けの姿勢である必要があります。
1-4. 平泳ぎ(ブレスト)
スタート・ターン後の一かきは完全に脚のところまでかくことができます。その間は水没が認められています。
スタート・ターン後の壁を蹴る時にはうつ伏せの状態でなければなりません。そして競技中は腕のかきと脚の蹴りのサイクルは一定であること、両腕の動作は左右対称でなければなりません。
さらに両手はスタート・ターンの一かきを除きヒップラインより後ろに動かしてはなりません。
泳ぎの各サイクルの間に頭が水面上に出ていなければなりません。両足の動作は左右対称で交互には動かせません。
そして両足の動作は推進力を得るためには外側に向いていなければならず、交互に動かすこと、ドルフィンキックは認められていません。
ターン・ゴールタッチは水面の上でも下でもよく、両手が同時に離れた状態でタッチしなければなりません。ゴールタッチ前の最後の一かき後は頭が水没が許されています。
2015年のルール改正で以前スタート・ターン後のドルフィンキックのタイミングは最初の一かきをしている間に行うこととされていましたが改正後は削除されました。すなわち、より水の抵抗を受けないスピードに乗ったタイミングで失格を気にせずドルフィンキックが打てるようになりました。
1-5. バタフライ
スタート・ターン後最初の腕のかき始めから体はうつ伏せであることターン後足が壁から離れた時にはうつ伏せでなければなりません。
競技中の両腕は水中を同時に後方へ運び、水面の上を同時に前方へ運ばなければなりません。
全ての脚の動作は同時で交互に動かしてはならず平泳ぎの脚の蹴りは許されません。
ターン・ゴールは両手が同時でかつ離れた状態でなければなりません。
1-6. 個人メドレー
それぞれの種目で定められた規則が適用されます。
1-7. メドレーリレー
それぞれの種目で定められた規則が適用されます。
1-8. その他
競技者はスタートしたレーンを維持しゴールしなければなりません。
リレーオーダーは競技まえに提出しリレーチームのメンバーは1つのレースに1回のみとなっています。リレーチームの編成は予選と決勝で変更が許されていますが、メンバーはその種目に正式登録した者と定められています。
水着・キャップ・ゴーグルは見苦しくなく人に不快感を与えてはならない。水着はFINA承認の水着であること、キャップは2枚の着用が許されています。
2. 失格の可能性の高い事例


前章で水泳の競技ルールで知っておかねばならない事項について競泳競技規則から抜粋しましたがこと細かく定められており、よく熟知しておかなければなりません。
以下に失格の可能性の高い事例について述べておきたいと思います。
2-1. フライング





でもスタート音の前に明らかなフライングの場合にはスタートのやり直しとなりますが、微妙な場合は競技は続行され、ゴール後にフライングを犯した選手は失格となります。
現在のスタート判定は目視だけでなく、スタート台は一種の体重計であって体重の変化でフライングの成否を判定していますからその精度は格段に向上しています。
従って、この判定にはリレー種目の引き継ぎにも生かされています。
2-2. 平泳ぎのドルフィンキック
前の章でも述べましたが平泳ぎの失格事例でよくあるケースがドルフィンキックの是非です。
スタート・ターン後浮き上がるまでの一かき1蹴り中のドルフィンキックです。以前はドルフィンキックの打つタイミングで失格となるケースが頻繁にあったのですが2015年のルール改正により減少しました。
2-3. 平泳ぎ競技中、頭の水没
私が学生時代によく犯した失格事例ですが当時はスタート・ターン以外は常に頭の水没禁止規定があったのですが、現在はストローク中に頭の一部が水面に出ていなければなりません。
2-4. 個人メドレーのターン中における泳法スイッチ
2019年世界水泳で200m個人メドレーで大橋悠依選手が失格となったのもこのケースですがこのケースで考えられることは背泳ぎから平泳ぎにスイッチしての最初の一かき一蹴り中のドルフィンキックだと考えられます。
彼女のようなトップスイマーが犯すはずのない失格事由ですが審判員の目にはドルフィンキックのかすかな動きに見えたのでしょう。わずかな集中力の欠如から下半身のストリームラインが崩れたのかもしれません。
背泳ぎから平泳ぎにターンする場合にはタッチするまでは背泳ぎですから90度以上のローリングは認められません。そして壁を蹴るときにはうつ伏せにならなければなりません。
平泳ぎから自由形も同様にタッチするまでは平泳ぎですから同時タッチでなければならないのです。
2-5. ゴールタッチ
ゴールタッチも失格となる可能性のあるケースです。
2-6. リレー種目の選手交代
リレー種目の選手起用においても失格となるケースがよくあります。
一人の選手が複数種目エントリーで疲労が激しい場合など的確な判断と配慮が必要です。
3. 失格を回避するための対策


競技中に失格はどうしても避けたいところです。でも緊張感の中で集中力が欠けるとどうしても日頃の癖がでてしまうことがあります。
緊張するなと言っても難しいレースです。緊張するのが当たり前、そんな中で以下に集中力を維持して競技をするかは経験がものを言うのかもしれません。
3-1. 練習でもルール違反は厳禁
でも、大橋選手のようなトップスイマーでさえその日の調子によっては集中力を欠いてしまうこともあるかもしれないのですから、いかに練習中の心がけが大切かと言うことを思い知らされます。
日頃の練習で失格になるような練習を続けていればレースでは必ず犯してしまいます。
例えば平泳ぎで片手タッチのターンや、水中での複数ドルフィンキック、あるいは片手ゴールなど背泳ぎでのターン時の90度以上のローリングなどです。
練習中苦しくなるとどうしても楽をしようとルール違反を犯してしまいます。そんな弱い心は厳禁!と自分を戒めて常日頃からルールに違反のない練習を心がけることが大切です。
・審判員の目と言うのも無視できません。自分ではそんなつもりでなかったり、明らかに違反事項は無いと自身があっても審判員の目には違反事例があるように見えたのですからそれは反論が成立しません。
従ってスタート・ターンにおいては不用意な動作は行わないように集中することが大切です。
そして違反と判定をされたときには、違反理由を必ず聞き取り再発防止を心がけるようにしたいものです。
3-2. スタート・ターンの練習
違反ケースの多いスタート・ターンは日頃からよく練習を重ねておく必要がります。
まずはスタートの反応です。耳がスタート音に反応して足が離れるまでのリアクションタイムを短縮する練習は数多く練習する以外にありません。





ウオーミングアップに気を使い過ぎサブプールで延々とアップを続けていると公開スタート練習に参加できなくなります。
この実際の自分のレーンのスタート台から飛び込むスタート練習は強い武器になります。
3-3. リレー種目の引き継ぎ練習
それからリレー種目での引き継ぎの練習も大切です。前の選手がゴールタッチを確認してからスタート台を蹴ったのでは大きなタイムロスとなります。
このリレーの引き継ぎ失格判定も目視以外に厳しいデジタル判定となっていますからしっかりとした練習が大切です。
3-4. 失格を恐れない


失格を防ぐための心構えや練習の重要性について述べてきました。
しかし一度失格を経験すると、それがトラウマになって日頃の練習の成果が100%活かされない場合もあると思います。
そしてついつい失格事例に心を奪われる場合もあるでしょう。でもそれは今までの練習で乗り切ってきたはずです。
失格を恐れずに果敢に攻めの気持ちでレースに集中すべきです。そして目標は最低自己ベスト、そしてその結果が大会記録の更新であったり、勝負に勝つと言う結果がついてくるはずです。その意味でも日頃の練習がいかに重要であるかを再度確認しておくべきだと思います。
スタート・ターン、そしてその前後、ストーク中はもちろんのことです。違反を無視した練習は決して本番のレースで失格の憂き目をみる可能性が高くなります。





なぜ世界記録は更新されていくのでしょうか?それは人間に与えられた特別の能力があるからだと思います。
水泳の競技ルールで認められている許容範囲は有効に活用して正々堂々と真っ向から立ち向かい記録更新につながるように頑張りましょう。
今の子供たちは体格は良くても
体力が落ちていると言われていますでも、世界記録は上がっています
それはなぜでしょうかいくら名馬でも
「より速く、日々努力するぞ!」
なんて馬は思いませんでも人間は世界新記録を更新できる!
それは
人間だけは、目標設定ができるからなのでしょう‼️
😀— 石原孝@水泳歴60年爺 (@hayaokitori) August 23, 2019
4. まとめ
水泳の競技会にエントリーした時のレース当日までの緊張感はあまりあるものです。そしてこれは経験した者にしか理解できないものであると同時に何にも代え難い思い出であり生きている実感!
自分自身、最高のパフォーマンスを発揮できる舞台です。この舞台であって欲しくない失格問題!
この失格対象となる事案は水泳ルールに則っており、このルースに従ってさえいれば防げるものです。従って失格は恥じるべきものであることは言うまでもありません。
でも、自分の意思とは別の次元で失格が起こりうる可能性さえ、無いとは言えません。
私が過去幾度もの失格を犯してきましたが最大の失態は競技中にパニックに陥り、コースロープに沿って泳いでおり、ターン後の浮き上がりで隣のレーンに浮き上がってしまう失態を犯した経験があります。
これなどはまさにパニックからくる集中力の欠如の何物でもありません。
このような違反行為をおこなさないためにも、レース中にはただひたすら自己ベスト更新の目標に向かって全神経が集中できるような精神状態でなければなりません。
そのために日頃の練習がとても大切であることは言うまでもありません。
ここで失格を防ぐ結論としては
・不安を払拭できる練習量の蓄積と自信
・競技会場の下見とプール環境をいち早く体感
・同僚とのコミニケーション
最後に水泳人生一度や二度くらい泳法違反などの失格の憂き目に出会うこともあります。でもそれはそれでまた良い経験です。
きっとマイナスにはならないと思います。
気を落とすことなく次回以降の教訓として活かしてこれからも末長い水泳人生を歩んでいただきたいと願ってこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いをいただき心から感謝しています。ありがとうございます。
なお、以下の関連記事も興味深い内容となっていますのでご一読いただけたら幸いです。



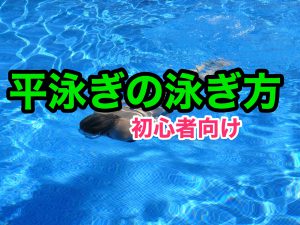













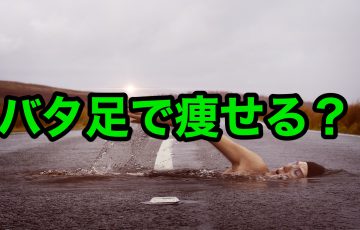











けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。