幼い子供達が水泳を習う時の必須アイテムと言えば、腰を浮かせるヘルパーとビート板!
特にヘルパーはバタ足練習に欠かせません。
もし親子でプールに行く場合このヘルパーを使うにはどんなことに注意すれば良いのでしょうか・・・?
可愛い子供達が腰にヘルパーを巻いてバタ足を習っている姿はとても微笑ましく凛々しい姿ですよね。
この腰に巻くヘルパーはとても重要な役割を持っており、このヘルパーで得る浮力を自力で生み出せるようになれば一人で泳げるようになります。
このヘルパーを上手に使って楽しく泳ぎましょう。

目次
1. 水泳用ヘルパー
水泳でヘルパーと言えば子供が水慣れレベルが終わり、クロールへ進級した頃に腰に巻いて腰が沈まないように補助する浮き具のことを言いますが。
子供の体型、泳力によって個数を変えることもできとても便利なアイテムです。
以前、私は次のようなツイートをしました。
可愛いですね!
青いビート板に顎をのせて青いヘルパーがしっかり腰に
青いゴーグル姿が凛々しい可愛い足をバタバタ
きっと直ぐ上手に泳げます…!真剣な表情がカッコいい pic.twitter.com/s7GwtcRdpK
— 石原孝@水泳歴60年爺 (@hayaokitori) August 16, 2019
では色々なヘルパーを見ていきましょう。
1-1. 腰用ヘルパー

クロールにも背泳ぎにも平泳ぎにもどんな泳法にも活用ができ腰が沈むないように浮力の補助をしてあげる浮き具です。
そして出来るだけインストラクターや親御さんがそばで頭を持ってあげたり、手を取ってあげるなどそばにいてあげることが小さな子供さんは安心して不安なく練習ができます。
少し大きなればヘルパーの数を2個、1個と浮力を小さくして自ら浮力を生み出せるように練習ができるでしょう。
1-2. アームヘルパー

両腕につけるアームヘルパーです。
水泳のためのヘルパーというよりも水深が背丈ほどあって、安全に水の中で楽しむための浮き具です。
水泳スクールでは水慣れレベルで使用するヘルパーとなります。水泳練習には腕が自由に動かせないのであまり使いません。
1-3. 大人用ヘルパー

子供用ヘルパーが浮力を変えて使用しましたが大人用は腰に固定させる点に重点をおいた構造になっており、自由に浮力を変えるというのはできません。
でも大人でもカッコ良くて水泳練習にはもってこいのヘルパーです。
1-4. ビート板

浮き具の代表格にはビート板があります。このビート板も大きさが色々あって私の通うクラブには板状の大きなものから、
上の画像で使っているような中型で前の部分がまるびをおびて水の抵抗が少なく、手前の方には顔を水につけても顔の邪魔にならないような形状となっているもの
それから一番小さくて腕の預ければ沈んでしまいそうな小さな浮力のビート板なども3種類あります。
そして一番小さなものは足の付け根で挟んでプルブイとしての活用方法もあって利用範囲の高いビート板です。
1-5. プルブイ


プルブイは足の付け根や膝や足首などで挟んで腕だけで水をかく練習に使うもので足を動かさず、なお足に浮力補助をするための浮き具です。
先ほどビート板のところでお話しした小型のビート板が右の画像です。ビート板の中央部の縦の部分に足で挟みやすいように凹んでいるのが特徴です。
腰に巻きつけるのではなく、両足の付け根で挟みつけて腰を浮かせるヘルパーとして活用します。
2. 腰が沈まない効果的な使い方

では腰に巻きつけるヘルパーの使い方についてお話しします。
まず対象は子供達です。ヘルパーをつけるポイントを説明する前にヘルパーをつける考え方を考えてみたいと思います。
2-1. ヘルパーを使うことの是非
腰に巻くヘルパーは自転車の補助輪と同様だと前段で申し上げました。
自転車が乗れるようになるには補助輪があった方が良いのか無い方が良いのかの考え方と全く同様だと思います。
早く自転車に乗れるようになるには転倒覚悟で最初から補助輪無しで始めるかです。
今回は腰につけるヘルバーですから水慣れができて水の恐怖心が取れたレベルの子供達ですとこのヘルパーがなければ多分泳げないと思います。
もっと話しを拡大すればヘルパーはもとより、ビート板さえ使わずにクロールを教えるとなれば、人はどうするかなのです。
私が子供のころ水泳を覚えたのは浮き具など無かった時代です。私の両親の親戚に漁師がいて、その漁師のおじさんの船に乗せてもらい、おじさんから無理やり海に放り投げられ、溺れかけながらいつの間にか泳げるようになったものです。
今の子供達にそんな危険なまねはできません。
水泳スクールに行ったとしてもビート板にヘルパーは必須アイテムです。
でもヘルパーに関しては使った方が良いのか、良くないのかは議論の分かれるところです。
そして慣れてくれば子供のレベル状況を見てヘルパーの数を3個から2個にさらに1個と減らしながら使っていくというのが的確な使い方だと思います。
2-2. 子供の恥じらい
子供さんは同じクラスで自分だけヘルパーをしているととても劣等感を抱くようになってきます。
この点が指導者側とすれば頭の痛いところです。
まあ、こういった子供さんの立場に立った配慮も持ちながら、隔たりなく上手に使っていく事が大切でしょう。
2-3. 効果的な使用方法
ヘルパーを腰に巻く時は必ず水に入る前、プールサイドでしっかりと腰に巻きつける必要があります。巻きつける紐が緩いと腰は沈みヘルパーは浮力で浮き、腰を締め付けてしまいます。
もちろん締め付けすぎるのも当然ながらNGです。
外す時もプールサイドに上がってから取り外すのも当然の事です。
3. ヘルパーを外すタイミング
腰に巻くヘルパーは子供ながらに、自分だけヘルパーを使っているは負い目を感じるようでヘルパーの使用は指導者側も気を遣うものです。
10数人の子供たちを一度の教える場合に子供たちそれぞれに個人差があり、ヘルパーが必要な子もいれば、不要な子もいます。なかなか難しいところです。
クラス編成には的確なレベル判定によるクラス編成が必要に思います。
3-1. ヘルパーの個数調整
ヘルパーは3個、2個、1個と数を調整する事ができますので、レベルを見て少しずつ数を減らして子供が自ら浮力を得られる泳力が身につくように配慮すると良いでしょう。
そしてヘルパーが不要と判断すれば進級させるなどの配慮が好ましいと思います。
3-2. クロール以外でのヘルパー使用
クロールでヘルパーを使用するのは一般的ですが、クロールから背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライへと進んでいく上で、泳法が代わり新しい泳法の泳ぎ方をマスターするまでは高学年といえどもヘルパーの活用は効果的です。
特に平泳ぎはキックがクロールと全く違い、足の裏で水を捉えるため、その習得までには時間がかかります。
習得までの間はヘルパーの活用と陸上でのイメージトレーニングが重要です。
3-3. ヘルパーの外すタイミング
ヘルパーは頼り過ぎるとなかなか上手にならないと考えがちですが、あまりそういう風に考えない方が良いと私は思います。
私が個人的に指導するとすればたとえ25mが泳げるようになってもヘルパーの使用はどんどん活用すべきと考えます。
もちろんヘルパーに頼りっきりでは泳力もつかず、上手になりませんが、
もし親御さんがお子さんを個人的に指導する場合などは、子供さんは甘えるかもしれませんが、ヘルパーを使う練習、使わない練習などとメリハリをつけて練習すると楽しく練習できると思います。
従ってヘルパーを外すタイミングなどといった悩みは不要だと思います。
もちろんヘルパーなど不要でどんどん泳げるのがベストですが、腰が沈んだ状態でいくら練習をしてもあまり効果的だとはいえません。
腰が沈む状態をヘルパーで補助してキック練習をすればキック練習も効果が期待できます。キックが強くなれば自然と全身の浮力向上にも役にたつでしょう。
そしてそれは大人にもヘルパー使用は配慮すべきと私は考えています。
4. 大人もヘルパーを使いましょう

前段で大人用の腰に巻きつけるようなヘルパーを紹介しましたが、子供用の紐で結ぶようなヘルパーでは大人には不向きであまりにもみっともなく見えます。腰に巻きつけるようなものではそれほどの違和感はないでしょう。
そしてその浮力補助を活用してスイム練習、キック練習を行うと良い練習になります。
4-1. 大人にも効果絶大
もし練習がダイエット目的に有酸素運動スイムであるなら、素晴らしいダイエット効果が期待できるでしょう。
もちろんターンなど水中姿勢において難点があるでしょうが、それは競泳ではなく有酸素スイムなのですからターンにこだわる事なく長時間のスイムに効果が期待できる事でしょう。
それにこのプルブイはターンするにも大きな抵抗にはなりません。ただ平泳ぎに関してだけは使えません。
4-2. プルブイはすごい!
プルブイの活用範囲はとても広く、プールに来れば是非一つプルブイを自分用に選んでその練習時間にはどんどん活用してドリル練習をしましょう。
・プル練習用として膝、足首で挟んで活用 ・足の付け根に挟んでヘルパーとしてスイムに活用
4-2-1. ビート板活用
このプルブイはキック練習に最適です。大きな浮力がありませんから、キック練習には最適です。そしてビート板のように大きくないですから水の抵抗も少なく、姿勢を正しくストリームラインを維持できます。
すなわちビート板のないキック(グライドキック)に近い練習ドリルが可能となります。
4-2-2. プル練習アイテム
両足でプルブイを挟んでプルだけの練習に大いにその効果を発揮できるアイテムです。
プルブイの名前通りの本来の活用方法です。このプルブイを足の付け根、膝、足首と両足の挟む位置でそれぞれ体幹部を同時に鍛えることが可能です。
4-2-3. 腰のヘルパー
先ほども述べましたが足の付け根に挟むながら泳ぐことでバタ足キック、ドルフィンキックが可能で腰への浮力補助が効いてスムーズなスイムが可能となり、フォームチェックなどの効果を発揮します。
この使い方をどんどん活用して練習効果をあげたいものです。
5. まとめ
以上、いろいろなヘルパーを見ていくと同時に、ヘルパー使用についての考え方と子供達に対する配慮のあり方、そして大人にもどんどん活用してバラエーションの多い楽しい練習を行って欲しい気持ちを込めてここまで述べてきました。
いかがでしたでしょうか、ヘルパーもなかなかどうして結構使い勝手の良いアイテムだなと感じてもらえたら幸いです。
子供達は高学年になればなるほどこのヘルパーを嫌がります。それはみっともないとの気持ちからだと思います。
その気持ちは本当によくわかります。
でもこのヘルパーはレベルに応じてまた違ったアイテムで代用することが可能です。体幹部が沈んでしまっては水泳の上達は遅れるばかりです。
ヘルパーを上手に活用することで体幹部の強化、正しいストリームライン、そしてキック力、プル力、総合的な泳力と技術とバランスが備わっていって欲しいと願っています。
そして何よりも単調で苦しいばかりの水泳練習にも楽しみと気分転換を与えることのできるアイテムとしてこのヘルパーの活用をどんどん進めていって欲しいと願いつつこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いをいただき心から感謝しています。ありがとうございました。
なお以下の関連記事もまた興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。
初稿:2019年8月18日
2稿:2020年11月28日

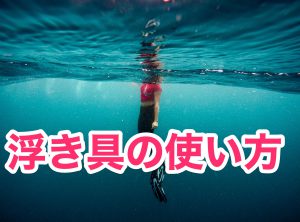










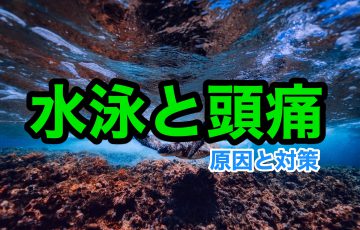












けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。