水泳初心者、特に泳げないカナヅチさんにとって「だるま浮き」が出来ないと嘆いている人もいるかもしれません。
また子供さんが水泳スクールに通わせる前に「だるま浮き」くらいはなんとか事前に教えておきたいとお考えの親御さんもいるかもしれません。
子供さんにとってはだるま浮きができれば水泳スクールに入会しても水泳の技術的には1歩前に進んでいることになります。
そしてまた大人のカナヅチさんにとって、だるま浮きができればもうカナヅチさん卒業です。さあ、次の段階に進んで数メートルでも泳げるようになりましょう。
とはいえ、なぜかこのだるま浮きはそんなに容易く出来るものではありません。
ではなぜ、難しいかというと人間は本来浮く生き物で、その上で大きく息を吸い込めば浮かないはずはないのですが、どうしても恐怖心や強い緊張感から身体が強張ってしまうからなのです。
どうぞこの記事で恐怖心や緊張を取り除いて、楽しく気持ちよく水泳をスタートさせていただきたいと思います。

目次
1. 水泳の基本「だるま浮き」のやり方
だるま浮きは両膝を両腕で抱えて背中がポッカリと浮いた状態を言うのですが、特段説明をするまでも無いと思います。
でも全く水泳をやったことがない子供さんがこのだるま浮きが出来るようになるまでにはかなりの個人差があります。もし子供の頃にこのだるま浮きが出来なければ大人になっても出来ず、カナヅチさんになってしまっているかもしれません。
このだるま浮きのやり方で最大のポイントは次の通りです。
・水の中で目を開ける
・呼吸(息を大きく吸って、止める、そして息を吐き出す)
・だるま浮き
この3つです。では一つづつ見ていきましょう。
1-1. 水に対する恐怖心を取り除く
初めてプールに入る幼い子供さんにとって親御さんから離れて一人でいることはこれ以上の恐怖はないと思います。
まず足が立つ水深で一人で立ち、そして一人で水の中で歩いたり飛んだりと水に慣れることから始まります。
そしてプールサイドを持っての伝え歩きからプールの中央部に進んでいきます。
1-2. 水の中で目を開ける
水慣れがある程度出来るようになれば、次に水の中で目を開ける事を経験します。今は誰でもゴーグルをしていますから特段水中で目を開けることは問題がありませんが、ゴーグルなしで目を開ける経験をすると水への恐怖心が一掃できるでしょう。
プールの中に投げ入れた沈んだ物を見つけて持ち帰る、両足を開いて立つ人の股くぐりなど子供に水中活動を経験させましょう。
1-3. 呼吸
次に呼吸です。
次に水の中に潜った状態で息を全て吐き出し息が無くなったら顔を上げる。
こうした事を体験させる事で子供達は浮力を感じることとなります。
1-4. だるま浮き
では次にだるま浮きを教えて人が浮く事を体験させる段階に入ります。今まで足がプールの床、若しくは水深補助台の上で足がたった状態でしたが、初めて足が床から離れ、浮いた状態を経験することとなります。
子供はだるま浮きで初めて浮く体験をしたこととなりこの段階から一気に上達が目に見えてきます。
次の段階はクラゲ浮き両腕を抱えずだらりと手足を脱落した状態です。
1-4-1. クラゲ浮き

このだらりと脱力した状態の次の段階は、両腕両足をまっすぐに伸ばし水平にした状態で浮く体験をさせましょう。これを伏し浮きと呼びます。
1-4-2. 伏し浮き

この伏し浮きでは体幹部の筋肉を使って両腕、両足をまっすぐにさせるように意識が必要となりかなりの進歩となります。
2. だるま浮きはなぜ難しいのか!

前章でだるま浮きについてポイントをそれぞれ解説をしましたが何と言っても難しい原因の一つが水への恐怖心を取り除くことに尽きるわけですが、なぜか子供によっては難してく出来ない子供もいると思います。
こうした子供達に共通する課題は次の三つです。
2-1. 緊張感を取り除けない
水慣れが出来るようになってもだるま浮きになるとどうしても身体が強張り緊張感を拭い去ることができない場合があります。
焦って、だるま浮きを強要させることのないように注意することだけは気をつけましょう。
2-2. 大きく息を吸い込めない
次に大きく息を吸い込めなくて十分な浮力が得られない課題があります。でもこの呼吸にしても緊張感と同じでよく遊ばせることが大切です。
2-3. だるま浮きが水泳練習だと錯覚
それからこのだるま浮きが水泳の練習で難しいものだとの勘違いが芽生えると厄介です。
さらに両膝を抱えるだるま浮きから両足を抱えずにクラゲ浮きを交えてさせるなど、単調にならないように気をつけてトコトン遊び感覚で楽しませるような工夫が必要です。
3. だるま浮きから次へのステップへ

だるま浮きを経験して難なくできるようになれば次の段階に移ることとなりますが、その前に必要なことは十分に呼吸コントロールを体験させて呼吸で身体がどうなるのか、浮力を体験させておきましょう。
3-1. 水中で息を吐いても浮く
先ほどからも述べていますが、呼吸をよく理解させる必要があります。
そして息を全て吐ききっても人の身体は浮く事を体験できればOKです。
水の中で息を吐き切ることが将来クロールに移る場合にも大きく役立ちますから、だるま浮きで単に浮くだけでなく、呼吸もしっかりと教えておきましょう。
3-2. だるま浮きから伏し浮き
だるま浮きからクラゲ浮きへと遊び感覚で体験した子供達は、かなりの上達が目に見えるようになってきました。では次に伏し浮きを教えます。
この伏し浮きができるようにならば遊び感覚の水遊びが水泳に変わったと言えるでしょう。その段階に至ればクロールに入っていっても十分に上達が早いことでしょう。
3-3. 背浮き
伏し浮きの次の段階は背浮きです。うつ伏せの伏し浮きから仰向けの背浮きを体験させましょう。
4. まとめ
水泳を始める最初の技術習得は浮くことです。
その浮くために「だるま浮き」を経験することはとても重要です。人の肺は言い換えれば浮き袋です。その大きな浮き袋を人体の中に持っている上半身を両膝で抱えて浮く体験ができれば子供であれ、泳げない大人であれ、大きな感動があります。
幼い子供は自分で浮くことができた時、その記憶は一生の物心として残ります。大人のカナヅチさんとてそれは同じです。
でもこの簡単なだるま浮きなのですが、なぜか難しくてなかなか完成しないのも事実です。
この記事では特に恐怖心を取り除くところに力点を置いて解説してきましたがまとめますと以下のようになります。
・遊びの中での水慣れ
・水中で目を開け光景を確認
・股くぐりなどで水中活動が楽しい事を知る
・だるま浮き
・だるま浮きを発展(伏し浮き、背浮き)
以上を焦らず慌てずにゆっくり時間をかけて水中での恐怖心を取り除いていきましょう。
さてこのような一貫した水泳練習を楽しみながらシステム化して教えているのが水泳スクールです。
いずれにしても、どんな練習であれ、水泳は決して怖いものでもなければ辛いものでもない事を教えるところから始まるのだという事を理解していただき、この記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いいただき心から感謝しています。ありがとうございました。
なお以下の記事も興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。

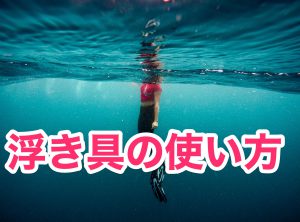





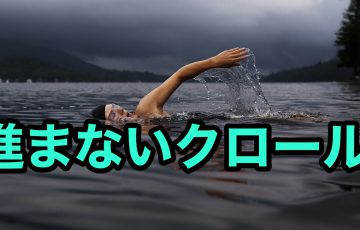



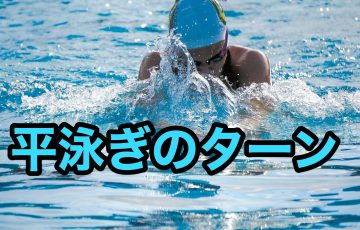













けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。