比較的飼育が簡単なメダカの育て方で難しいと言えば稚魚を沢山残すことだと思います。
ゴールデンウィークを迎える頃、水が温み、水温20℃くらいになるとそろそろ産卵期を迎えます
夏を過ぎる頃までダラダラと言えば語弊がありますが、産卵を見落とし、気がつくと小さなメダカが目につくことがあったかと思いますが、この記事でメダカの育て方を理解されて、これからはどうぞメダカの稚魚を沢山、成魚に育てて欲しいと思います。

目次
1【メダカの育て方】稚魚生残率の向上のコツ
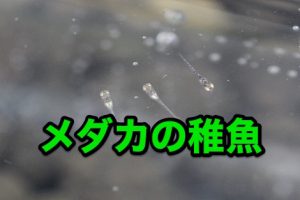
メダカの産卵と卵の管理そして孵化時点における飼育については別の記事で詳しく解説していますが今回は孵化後数日でヨークサック(卵の栄養嚢)が取れてメダカの仔魚が自ら餌を捕らえて餌としなければなりません
そしてそのメダカの稚魚(針子)の時期が一番、生残率が悪く、ほとんどが死んでしまいます。
自然界や屋外飼育では稚魚が身を隠す水草などが豊富なためある程度生き残ります。
でも屋内では親を含む成魚と共に稚魚を飼育するのは無理があります。
メダカは共食いをするのかという疑問もありますが、成魚の口に入るほどの孵化後すぐの稚魚であれば自ずと成魚の口に入ってしまします。
そして2月ほどすると2cm程度、半年くらいで3cm程度で成熟期となります。
別水槽が困難な場合であっても稚魚を育てるのであれば親と同じ餌を与えるまでは別水槽で育てるのが良いでしょう。
親と同じ餌と言いました。これは正しく稚魚は成魚と異なって餌が必要です。
稚魚の餌
さらに同じ餌を与えていると稚魚は全く餌を口にすることができず死んでいってしまうということとなります。
もう少し詳しく解説すると孵化直後のメダカはヨークサックを抱えています。そしてヨークサックが取れて自ら摂餌する必要がありますが、その時点の稚魚は餌を見つけて泳ぐというよりは漂い彷徨っているような動きです。
そんな稚魚が自ら餌を捕らえるのは不可能です。
動物プランクトンとしてはゾウリムシ
甲殻類プランクトンにミジンコそしてブラインシュリンプ
甲殻類プランクトンと言っても小さなミジンコともう少し大きなブラインシュリンプがあります。
(ただ市販されているブラインシュリンプは耐久卵で販売されているので孵化させる一手間が必要ですから初心者には不向きでしょう)
そして少しずつ配合飼料を餌付けして最終的に配合のみにしていけば良いでしょう。
2 稚魚の隔離飼育

共食いも無いとは言えませんが餌は成魚が食べ尽くし、稚魚は食べるチャンスが限りなく少なく衰弱して死んでしまいます。
このことは前章でも述べましたがとても深刻な問題です。
稚魚の生残を高めるには以下のような配慮が必要となります。
隔離
まず隔離して飼育することが必要です。
ここでこの隔離方法を紹介します。
水草に付着している受精卵を回収するには水草ごと隔離してしまえば事足りますが、動き始めた稚魚を回収するには底掃除に使うサイホンを使います。
稚魚が通過できる直径のビニールチューブを用意してサイホンで回収しましょう。
稚魚に対峙するまではチューブの途中を閉じておき、稚魚の背後から吸い込みましょう。比較的簡単に稚魚にダメージなく回収することができます。
餌
前章でヨークサックの取れた頃からの餌の種類については紹介しましたがもう少し詳しく解説したいと思います。
成魚に与えている餌はメダカ用の配合飼料ですが、この餌の粒径は大きくメダカの稚魚の口には入りません。それに稚魚には馴染みのない餌であるため餌の効率が良くありません。
従って、餌を考える時には常に稚魚の口に入るか?これを考えるのが原則です。
それに稚魚の泳力です。稚魚は餌の捕獲のための泳力が十分ではありません。
餌と遭遇する機会が少ないとそれだけ成長が遅く、命の危険となります。
ゾウリムシ、ミジンコなどの餌がメダカの稚魚が難なく食べることのできる環境を作ってやりましょう。
この植物プランクトンはグリーンウオーターやクロレラです。そしてこの植物プランクトンが豊富ということは水槽の色が緑色を呈しメダカの気持ちを和らげストレスも抑えます。
餌を与えるタイミングですが、成魚では食べ切る量を与えるのが原則ですが、稚魚の場合は配合飼料に転換が終われば成魚と同様の考え方ですが、プランクトンフェーズでは1日に1回程度餌を補給する程度で良いかと思います。
常時餌と稚魚が共存しているバランス均衡がベストだと言えるでしょう。
メダカの稚魚、そして植物プランクトンと動物プランクトンとの食物連鎖がうまくいけば稚魚にとって最高の飼料効率となります。
3 観察眼こそ最大の技術

メダカの稚魚をいかに育てるかは隔離と餌について良く理解されればあとは飼い主の知恵でいかにも応用が可能です。いろいろと試していただいてそれぞれにご事情に合わせて上手く育てていって欲しいと思います。
それからもう一つ大切なことを言いますとそれは観察力です。
もちろん初心者の飼い主が初めからベテランの観察眼など持ち合わせていないのは当然です。でも生き物を可愛がる心さえあればその浅い飼育経験も日々の観察の積み重ねがどんどん観察眼が養われていきます。
気が向いた時に観察して記録するのではなく、必ず、1日最低2回観察して記録しておきましょう。
大切な観察項目は以下のようになります。
・給餌時刻
・摂餌行動
・異常個体
・水槽全体の状況
・飼育者の総評
浮遊餌の計量
成魚の給餌は目で見て観察できますが、稚魚の場合には水槽内にどの程度の餌が存在するのかはどうやって確認するか?
それは飼育水槽が小さいですから全体的に餌が充満していると想定して1mmLのピペットや細いガラス管に吸い取り数を数えて計量します。
でも、その餌が生きているのか死んでいるのか餌の活性力もしっかりと観察して欲しいと思います。
観察日誌は強い財産
観察日誌は飼い主にとって大きな財産です。飼育中のトラブルはこの日誌を見ればそのほとんど解決の糸口が見出されるはずです。
1年前の拙い日誌もとても貴重な参考書です。是非メダカに限らず生き物の飼育には是非観察日誌を習慣にしたいものです。
4 まとめ
今回の記事はメダカの稚魚をいかに回収して稚魚を多く残して育てるかに絞って解説してきました。きっと少なからず新しい気づきがあったことと思います。
でも難しいことは何一つなく、自分自身が親なら子供を想い、愛おしい気持ちになれば当然のことだと感じてもらえたらそれでこの記事の趣旨は理解されたことでしょう。
メダカを飼い始めて冬を越し、暖かくなって気がつけば小さなメダカに気づくことがありますが、この過程には産卵、孵化、成長という劇的なドラマがあったことを見失っていたことを示しています。
これからはどうぞ、慈悲深い観察眼でメダカを育てていって欲しいと思います。
では最後にまとめておきましょう。
メダカを育てるのは難しいことではありません。毎日しっかりと観察していれば大きな感動を飼い主に与えてくれる命のたくましい営みに接することができるはずです。 でも、そのためにも、メダカの産卵にはいち早く気づき、いち早く、隔離して、成魚とは異なる飼育環境を作ってあげて稚魚をたくさん残して日々の暮らしを豊かなものにしましょう。 でも私たちは決して繁殖を目的にしているのではありません。増えたメダカの処分も考えておきましょう。 メダカは絶滅危惧種として知られており、私たちが接するメダカは作られて種類で、決して自然界に放流してはなりません。 このことだけはしっかりと頭に入れてメダカの飼育を楽しみましょう。
以上申し上げてこの記事は以上とさせていただきます。
最後までお付き合いをいただき心から感謝しています。ありがとうございました。
なお、以下の記事も興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。

























けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。
私の現役時代は魚類の試験研究現場で長年勤め、魚の生き死について色々なケースを見てまいりました。読者の皆様に参考になる情報を提供できると思います。