可愛くてカラフルなグッピー!自宅のリビングはまるで美しいアクアリウムの出現にワクワクしていることでしょう。
でも心配の種は餌やり・・・
グッピーは私達人間と同じく生きとし生けるもの!寝食を共にするわけですから、ご自身の食事タイミングと併せてはいかがでしょう・・・
それもご自身を戒めるためにも腹八分を心がけるのが原則だと思います。
さあ、餌やりの楽しさ、重要なグッピーの食事です。しっかりと観察して喜びを共有していきましょう。

目次
1 グッピーの餌やり頻度

では早速グッピーの飼育で一番大切な餌やりについて解説していきましょう。
餌やり(給餌)はグッピー特有の給餌方法があると言うものではなく、魚を飼育するためにはほぼ同じようなやり方で、難しいものではありません。
ある人は1日1回、またある人は1時間毎など定期的に小まめに給餌する人もいることでしょう。
飼い主の生活リズムやスタイルによってグッピーの給餌を考えてもらえれば特段問題は起こりません。
グッピーを知ろう
まずグッピーとはどんな魚なのか少し説明したいと思います。
グッピーはメダカの一種と考えがちですが、純然たるカダヤシ目のグッピーと言う種類の魚です。グッピーの特徴は卵胎生を行う魚として有名です。
オスは3cm〜4cm、メスは5〜6cmでメスは大きくメダカやカダヤシに似ており、オスは小型ながら彩が美しい
グッピーは主にシンガポールで養殖された外国産グッピーと日本国内で繁殖しされた国産グッピーと二分され、熱帯魚だけに耐寒性がよくなく、日本の自然界、特に冬季間の野外で飼育するのは難しいとされています。
餌やりの原則
餌やりの原則はどんな魚に対してもほとんど変わりませんが、グッピーの成長に見合う適正な餌やりが基本です。
1日に一回でも3回でも、少量を小まめにやるのも良いでしょう。
1回の給餌量を知り、毎日同じリズム・頻度で給餌するのが好ましいです。
そしてやり過ぎないことです。
グッピーを購入して自宅の水槽に初めて入れるとき、餌をまず与えると思いますが、ショップから移動中は基本空腹であることが多く、自宅での最初の餌やりの時ですが、案外移動ストレスから餌を食べないことが多いことと思います。
その時は給餌をしばらく間隔を置いてストレスから開放されてから餌をやるようにしましょう。
餌のやりすぎに注意
本来魚は飢餓状態で暮らしてます。従って飢餓には慣れっこというか彼等の遺伝子には飢餓に耐える能力が備わっています。
従って養殖用として飼育されている魚が大きくなるために餌を食べるのと、観賞用の愛玩グッピーとはそもそも飼育管理の基本的考え方がまるで違います。
これは人間にとっても同様なことが言えます。
一番危険なことは餌のやりすぎです。やり過ぎにより魚は肥満化となり、よく食べる魚とあまり食べない魚との群が形成され、大きな魚や小さい魚を攻撃したりします。
魚自体に大小差がでないように、適正な給餌量を守りましょう。
そして餌には浮く餌と沈む餌があります。このどちらを選ぶかは水槽底の状況や掃除のこともよく考慮して餌のタイプを決めると良いでしょう。
餌のやりすぎで考えられるリスクを列挙すると
・餌の食べ残しによる水質悪化
・食べ過ぎによる病気
などが考えられ餌のやりすぎは良いことは何もありません。
餌やりの頻度
餌やりの頻度は飼い主の実情に合わせて1回でも2回でも3回でも良いです。
飼い主の食事に合わせて食事の時間を共有するというのが私はおすすめします。
でもこの餌の頻度というのはそんなに神経質になる必要は無いと思います。
2 しっかりと摂餌行動を観察

では次に摂餌行動の観察について解説をしていきます。
餌やり中におけるグッピーの摂餌行動を具体的かつ明確に言葉にして記録することが大切です。
でもそもそも摂餌行動そのものが無いケースが多いことでしょう。
餌やり中の摂餌行動を観察
水槽にグッピーを移設してしばらくの間は移動ストレスで餌を食べないかもしれません。そんな時には無理に餌を与えないようにしましょう。
底に沈んでしまう餌では水槽の底が腐敗してしまいます。
そのうち、グッピーは空腹となり餌やりの時に元気に摂餌行動をとるようになります。
給餌する餌を食べている間は与えて大丈夫です。でもグッピーがお腹一杯になるともう餌は食べなくなり見向きをしなくなります。
ここまでの餌の量が1回に与える最大給餌量です。
そして餌やり中に元気に摂餌行動をとっ餌を食べるようにしつけましょう。
摂餌行動の異変にいち早く気づく
その事が飼育技術の向上という財産が形成されていくことでしょう。
3 グッピーの餌と病気の関係

餌と病気の関係ですが、グッピーも人間と全く同じと考えれば良いと思います。
人が病気になるのは怪我、皮膚病、そして風邪などの感染症ですよね。そしてこれら病気の原因はというと、ほとんどがストレスや食べ過ぎによる免疫力の低下だと思います。
グッピーも同様に考えればよく理解できると思います。
では一つづつ解説していきましょう。
怪我
グッピーで考えられる怪我とは美しい尾びれが共食いなどでボロボロになってしまう場合があります。
そして大きなグッピーは小さいグッピーの尾びれを共食いします。
大きなグッピーは餌が不足気味なのでしょう。
こういう大小差が現れたたら別の水槽を用意した方が良いかもしれません。
尾びれが傷んでくると尾くされ病とか他の病気の原因ともなりかねません。
とは言え、この怪我に関しても給餌が大きく影響を及ぼしている事がわかります。
皮膚病
この治療には塩水に浸すなどの治療方法がありますが原因はというとやはり、食べ過ぎや極度の飢餓状態による免疫力の低下、そして活動の低下から寄生虫やカビなどになどにより引き起こされる病気です。
しっかりと元気に食事をすることの重要性をここでも物語っていると思います。
感染症
そして感染症です。細菌やウイルスによる感染症です。人に風邪があるように魚にもあります。
食べ過ぎや極度の飢餓状態による免疫力の低下により感染リスクが高くなってくるのでしょう。
正しい給餌習慣(腹八分)
以上のように給餌というのはとても大切な飼育管理であることを理解していただければ初心者から一挙に中級者へ突入となります。
そして繰り返しになりますが、日々の観察力が過去の記録との比較において、早期に病気や不足の事態を回避できることとなります。日々の観察こそ魚の飼育管理の最重要だと頭の片隅においていただければよろしいでしょう。
4 まとめ
グッピーの給餌に関して必要な情報を盛り沢山で解説してきました。
何と言っても餌やり(給餌)は飼育管理上大切なことであり、飼い主にとっても元気に餌を食べるグッピーの姿は癒されるものです。
でも現実は飼い主の見ている前で餌を食べている姿を観察するのは非常に稀だと思います。
それは餌のやり方に問題があります。
餌の量、そして頻度を考えてしつけましょう。何と言っても、餌の食べ方は大切な魚にとっての診断チェック項目なのですから・・・
ではここで餌やりのポイントを今一度整理しておきましょう。
・餌は飼い主の目の前で摂餌行動があるようにしつけましょう。 ・一度に大量に給餌するより飼い主の食事リズムの合わせた頻度で。 ・摂餌行動は大切な観察チェック項目です。 ・グッピー購入時ショップで与えていた餌を継続するのが一番適切 ・病気などの症状が出た魚や別水槽に隔離し絶食です
以上のことを知識として知っていていただければ安心してグッピーとの暮らしが共有できることと思います。
毎日、寝食を共に元気に充実した毎日を過ごしましょう。
ということでこの記事は以上とさせていただきます。最後までありがとうございました。
なお以下の記事も興味深い内容となっていますのでご一読いただけたら嬉しいです。









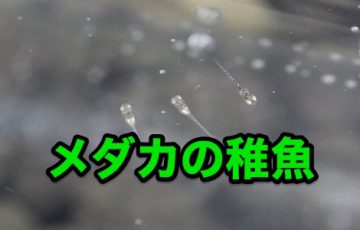














けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。
私の現役時代は魚類の試験研究現場で長年勤め、魚の生き死について色々なケースを見てまいりました。読者の皆様に参考になる情報を提供できると思います。